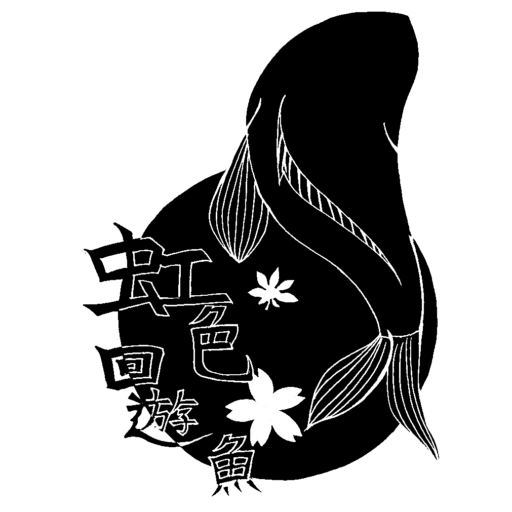10、潮の香り
昔々。本当に昔のこと。まだ小さすぎるぐらい小さくて、お父さんとお母さんと手を繋いで歩いていた頃かもしれないぐらい昔のこと。海の近くの大きな水族館。電車に乗って何時間も揺られながら、眠いとぐずりつつ水族館が近くなっていって、それから。
ステンドグラスがキラキラと輝いていたこと。それから潮の香りが濃かったことを覚えていた。
「マスター、それ、今考えること?」
「ごめん、でも」
なぜだか思い出してしまう過去の記憶。それは敵のスキルによって強制的に思い出されるものであって、藤丸立香が思い出そうと思って思い出していたものでは無かった。オベロンは敵の一匹をなぎ払いながら、頭を抱えているマスターに気がついて、短く舌打ちをしてから腕でマスターを引き寄せた。
「まったく、きみってば本当にこんな時に何を思いだしているわけ?」
「ご、ごめん」
「きみの国に言い言葉があったよね。ゴメンで済めば警察はいらない、だっけ?」
「確かにあるけど……、オベロン、敵の狙いは?」
「大方、司令塔を混乱させて指揮系統をめちゃくちゃにすることだろう。ただおあいにく様。俺らは無茶なマスターに散々扱き使われているからね。マスター一人が行動不能になったところで俺たちの動きが鈍るわけが無いだろ?」
「……」
なぜだか分からないけれど怒っている。それもかなり。
敵を一匹、また一匹と倒していき、そうして最後の一匹の元へ降り立つ。そうして鎌をかまえて敵の首元へ。真っ直ぐ振り下ろしたのだった。
小さな頃。流木を拾った。海を何年も漂って曇りきったガラスを拾った。ピンク色の薄い貝を拾った。全部全部宝物であった。
大事な大事な、たからもの。りつかの大事なたからもの。
「おい、マスター?」
「あれ、おべ、ろん? どうしたの?」
「きみってば、本当に暢気だな。俺が最後のエネミーを倒した瞬間にきみは倒れたんだよ」
「あ、ゴメン。心配かけたみたい、だね?」
「心配はしていない。ただ、エネミーを倒したらこれが出てきたんだけど? なんだいこれは?」
「えっと?」
貝殻と流木とシーグラス。それらが入った……小瓶?オベロンが手のひらでコロコロと転がしていたそれを受け取る。
どうしてこんなところにこれが、と思いつつ、どこからとも無く潮風を感じて目を見開いた。思い出せないほど昔の話。本当にどうしてだか分からないけれど、幼い頃に手に入れたたからものを入れていた瓶とそっくであった。
「オベロン、これ、最後のエネミーから出てきたんだよね?」
「ああ、そうだけど。もしかして、そのエネミーのところに連れて行けとか……マジかよ」
本気と書いてマジと読む。そんな表情を浮かべた立香にオベロンはため息をつきながら肩を貸して、倒れて消えかかっているエネミーに近づいた。
立香ちゃん、ゴメンね。いつものように極小特異点ができたのは数日前であった。その特異点では、日本で言う付喪神のような存在がエネミーとなって現れる世界。忘れ去られ、それを悪い気へと変貌させた付喪神。それらが集まって、そうしてできた一柱の神を倒すのは本当に大変だったのを記憶している。
もしかしたら、これは、この瓶を内包していたものは私の持っているこれの付喪神のような存在なのでは。そう思い、近づいたけれど、残念なことにその存在をはっきり見ることはできなかった。形は崩れ、すでにほぼ中身も無くなっている。ただ、分かるのは懐かしい潮の香り。それだけであった。
「……リツカ、帰るぞ」
「うん」
背を向けたけれど、肩越しに振り返る。溶けて、無くなる。最初からそこに何も無かったように。それでも、忘れていた記憶をよみがえらされるように、強烈に潮の香りから記憶を取り戻してはいた。
「リツカ、俺はきみのことだって人間のことだって好きでは無い」
「うん、それは分かってる。忘れるから、でもあるでしょ? 私も現に忘れてたし。でも思い出したし、これからも今のできごとだって、オベロンと出会ったことだって思い出すよ?」
「……勝手にしろ」
「うん、勝手にする」
「……」
潮の香りと蟲の声。私の恋した蟲のひと。
思い出と共に残るだろうこの記憶を忘れたくない、思い出せるようにしたい。そう思いながらぎゅっと小瓶を握るのだった。