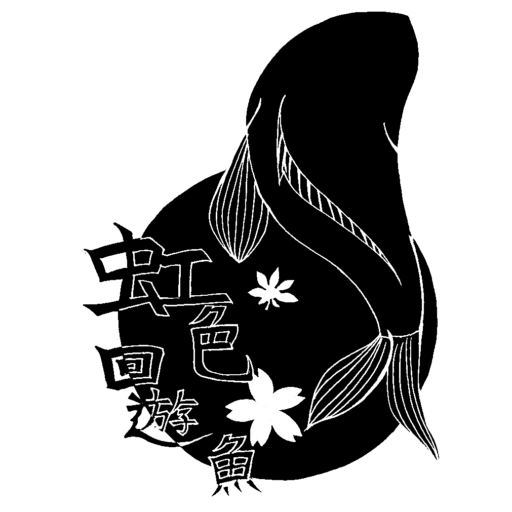8、「ありがとう」
「マシュ!」
目の前で立香がマシュに体当たりをする。マシュが先ほどまでいた場所にはワイバーンの鍵付けが振り下ろされ、彼女のマスターである藤丸立香は背中を大きく切りつけられていた。
「立香ちゃん、君がしたことは一歩間違えたら……と言っても君は同じ場面があったら同じことをするんだろうね」
ダヴィンチちゃんは反省室、もとい彼女の部屋で立香を見ながら語りかける。その目には全てが分かっていると書かれているよう。
マシュの命は一度は亡くなっていたかもしれない。先輩という立場。それだけでは無い。駆け引きなしに、立香にとってマシュは守りたい存在であった。
「うん。間違ってはいるかもしれないけど、どうしてもこれだけは」
「君が今回飛び出した結果だけど、倒れた君をワイバーンが追撃しようとして、それをオベロンが追い払うために宝具を使用。今回は同行サーヴァントとして彼に付いてきてもらってはいたけれど、分かるよね?」
「はい」
オベロンは他のサーヴァント達と一緒に戦闘パーティーに組まれていたが、それは組まれていただけと言うもの。実際にはオベロンのバフや宝具を利用せずに場を切り抜ける練習を行っていたのだった。
「それでだね、彼は宝具封印を簡易的にかけていたものを破って宝具を使用したんだ」
「それって……!何かあったんですか?」
「まあ、その……人間で言ったら筋肉痛みたいなものかな。無理矢理宝具を使用したからしばらくは宝具は使えないし、スキル封印も追加されて、簡易的な弱体状態になっているってところかな」
ついでに言っちゃうと、君が倒れたところへの追撃を身を挺して受けたから、身体的にもダメージは負ってるね。さっき目を覚まして悪態をついていたから問題は無いと思うけど。
大丈夫だけれど、身体的にも魔力的にもダメージを受けている。そう聞いて立香はドキリとする。自分が傷つけば良い。そんなことは勿論考えていない。それでもあのオベロンが身を挺してまで自分のことを庇ったことに、その結果に、理解が及ばない。どうして、どうしてあの彼が。
立香とオベロンはいわゆる恋仲だ。ただその前提にはマスターとサーヴァントとしての信頼、もっと言ってしまえばお互いがお互い最良の判断をして行動するというところに信頼を置いている。そう立香は考えていた。この場合で言ってしまえば、マスターを助けるのは確かに大切なことだが、それであるならばワイバーンを攻撃、撃破してしまうことが最善だったのでは無いか。そう思ったのだった。
「……かちゃん、りつかちゃん?」
「あ、はい。ごめんなさい」
「ううん、良いんだよ。まあ、まさかオベロンが君を庇うなんてこちらでも考えてなかったからね。うーむ、これはあれかな? 愛ゆえ、と言うやつかな?」
「あ、愛って?」
「うん。古今東西愛は人を惑わせる、なんて言うだろう? それにオベロンはもともと……と、アラートだ。げっ、シオンからの連絡だ」
逃げ出したいけれど逃げ出せるような状況じゃ無いんだよなぁ。アラートを消しながらもダヴィンチはニヤニヤと立香を見つめる。
「オベロンは決して愛を持たない。最後の戦いの時にそう言われたんだろう? だから、愛について疑っている。けれどさ、考えてごらんよ。英霊召喚は双方合意が無いと呼ばれないんだよ。その時点で何かしら彼だって思うところはあるんじゃ無いかな。こいび」
「やあ、ダヴィンチ。マスターはいるかな」
「ああ、オベロンくんじゃないか。体調はどうだい? 彼女の後に呼ぼうと思っていたんだけど、シオンから連絡があってね。ちょうど良かった」
「ああ。気分は、最悪ってほどでは無いかな。しばらくは休ませてもらうけど。それで、マスターを借りていっても良いよね」
「もちろんだとも。ちょうど彼女との話も終わったところだしね」
ほら行った行った。立香は白い外套を纏ったままのオベロンと一緒に外に出された。去り際に押される後ろを振り返ると、ダヴィンチの顔は少しだけまだ顔がにやけており何を考えていたのかは一目瞭然だけれど、それでもオベロンと話すことができるならと思い、立香は素直に廊下に押し出された。
「オベロン、その」
「なに? 謝罪でもしてくれるつもり? それは良かった。いくら猪のようにお転婆でもあんなことをされるなんてね。全く、サーヴァント冥利に尽きるような活躍をしてくれたじゃあないか」
「それは、ごめん」
「まあいいよ。暫く休んでいれば回復する程度だ。ブリテン中を動き回っていた時よりは酷くない」
「……」
本当に悪いと思っている。それでも、もう一度同じような状況があったら今度は別の行動が取れるか。そう問われても首を縦に振ることはできないのだった。
「本当にきみは、まあいいさ。乗りかかった船だ。最後までマスターのサーヴァントであり続けてあげようか」
「……、ありがとう」
「皮肉に真っ直ぐな返事を返すとか、大丈夫か? 怪我をしたときに頭でも打ったか?」
「そんなことは無いよ。でも、本当にありがとう」
オベロンの言葉はいつも通りに歪んでいる。それでもどこかに立香を心配する気持ちが見えてしまう。それはもしかしたらさっきダヴィンチから聞いた都合の良い答えのせいかもしれないけれど。それでもそうであったら良いなと思い、立香はオベロンに笑顔で言葉を紡ぐのだった。