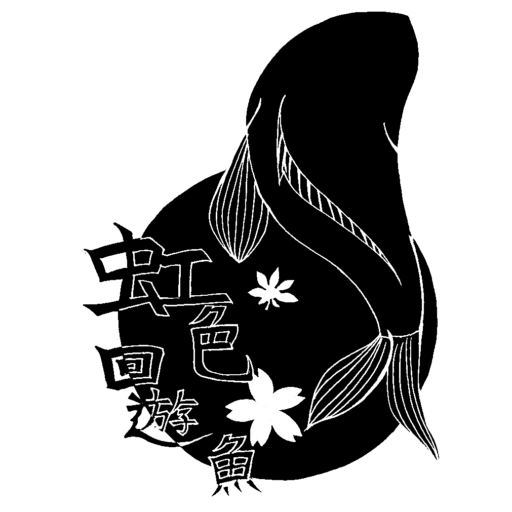17、別に何ともない夜
大切なひととホテルで一夜と言ったら何を思い浮かべるだろう。家族旅行? 女子会? それともちょっとえっちな考えだろうか。残念ながらそのどれでも無い。
藤丸立香はただいまオールキャラギャグと面打って、サバフェス二の原稿と向き合っている。今回もジャンヌオルタちゃんを中心とした面々でサークル参加申請をしていたのだった。
「はいはい、そろそろ休憩時間ですよ。サーヴァントはともかく、人間のマスターは休憩入れてくださいね」
「ありがとう、ロビン」
じゃあ休憩に入るね、と部屋を出て自分の部屋へ。ああ、疲れた。時刻は午前一時。普段だったらもう眠っているだろう時間まで作業を行っていたからか、それともずっと椅子に座って作業をしていたからなのか、肩がバキバキという音を立てる。確か明日の作業時間は朝の八時からだったから、今から軽くシャワーを浴びて、髪を乾かすのは……自然乾燥で良いか。そんなことを考えながら自室としてあてがわれた部屋を開いた瞬間、ラベンダーの香りが鼻腔をくすぐった。
「やっと戻ってきたのか」
「オベロン?」
あてがわれた自室にはキングサイズのベッド。それからベッド下収納と入ると曇るタイプのバスルーム。部屋の真ん中には小さなガラス製のミニテーブルといった、ベッド以外は比較的簡素な部屋であった。その部屋のベッドの上でポテトチップスをこぼしながら寝転んでいるオベロンはあくびをしつつこちらを横目で睨む。
「やあ、マスター。いい顔をしているじゃないか。そのメイクは最近の流行なのかな? 目の下の黒い影が最高だな」
「これは、ゴメン。確かに休憩とか入れてないし、アンプル打ちたいとか思ってたけど、そこまで怒らなくても良いでしょ」
「俺が怒ってるって?」
「うん、怒ってる」
怒っているのは分かるし、それから少し心配しつつ応援してくれているのも分かった。言葉の端々から感じる毒はいつものことだけれど、その中でも細かいところを観察して的確に疲労を指摘していたし、部屋に入ってきた時に感じたラベンダーは曇っているバスルームから香っているように感じるのだ。
「きみは、そうやって都合の良いように捉えるのをやめた方が良いと思うんだけど?」
「そうかな? でも、こうやって不都合とか特になかったし」
「……そうかよ」
「それより、お風呂入ってきてもいい? あと、髪乾かすの手伝って欲しいんだけどダメ?」
「質問と注文が多いな、俺のマスターは。……いいよ。どうせ放っておいたらそのまま自然乾燥だとか言ってベッドが濡れるのも気にせずに眠るんだろ? ベッドで寛ぐのはきみだけじゃ無い。少しは気を遣ってもらわないとね」
「わーい、ありがとう」
「うわ、全く心がこもってないぞ、こいつ」
ブツブツと言うオベロンをそのままに、脱衣所へ向かう。足取りは思いのほかふらついていて、あれ、と思ったときにはプツンと意識が途切れたのだった。
ごうごうと音が聞こえる。頭の下にはふわふわとした布が敷かれていて、髪の毛はそこに広げられ、風が当てられている。なんだろう。心地よい香りにもう一度眠ってしまいたいと言う欲求に駆られる。それでも状況を思い出して、目を開いた。
「あ、起きた。おはよう、マスター?」
「お、オベロンさん、おはようございます」
「まさか自分の体力の限界を理解せずに行動するなんてね。女性の身体を重いなんて言いたくは無いけど、お風呂に入れるのは苦労したんだぞ?」
「ええと、お風呂に入れてくれたんですね」
二臨の比較的もふもふとしたオベロンに後ろから支えられるがままにゆっくりと身を起こす。髪はしっかりと乾いており、ヘアオイルでも寝ている間につけてもらったのか、しっとりとしていて、良い香りがする。思わず自分の髪の毛を嗅いでいるとため息をオベロンはついた。
「まったく、アルトリアといいきみといい。少しは自分が女の子であることを自覚したらどうなんだい?」
「ん? 自覚はしてるよ?」
「生物学上じゃなくて、だよ? 流石に意識の無い状態で異性に風呂に入れられたりしたら嫌がるものじゃ無いかい?」
「そういえば……」
「そういえば、じゃないだろ。流石に風呂には入れてない。ただ、髪の毛だけは洗わせてもらったけどね。なんだよ、あの汚れ方は」
「あはははは。取材中に七面鳥の群れに襲われてですね」
砂にまみれた七面鳥たちに追われながら行った取材。取材中に頭に乗られたりもしたっけ、だなんて思い返す。
「とにかく、だ。少し寝たらすっきりしただろ。髪を水に濡らさないように風呂に入ってきなよ」
「うん、ありがとう」
別にホテルの一室に二人きりでいたって何かが起こるわけじゃ無い。それでもこうやって女の子扱いしてくれたり、心配してくれたり、他にも先を考えて準備をしてくれたりと、沢山のことをしてくれる恋人につい甘えてしまうのであった。