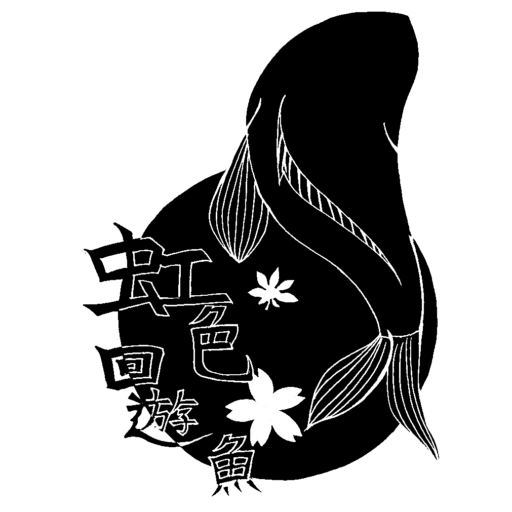60、魔力供給
「オベロン! これでお願い!」
令呪が輝き、強制的に魔力が充填される感覚を得る。ああ、もうめんどくさい。目の前の奴らの全てを終わらせてしまおうと、集ってくる虫たちに舌打ちをしつつ、影形もなくなる。そうして、全てを飲み込んだ。
「ありがとう……ってどうしたの?」
「別に? 何でも無いよ?」
「何でも無いってことは無いでしょ?」
宝具を相手に向けた瞬間、死を悟って暴れ出したそいつらに、腕を、足を、身体を引き裂かれる感覚がした。もちろん虫竜の姿をしているからそんなわけはないのだけれど、それでも幻痛のようなもので身体が疼いていたのだった。
それを悟られたくなくて、そんな一撃を間抜けにも受けてしまっていた自分にいらだちがあって、思わず刺々しい言葉を口にした。
「ったく、五月蠅いな」
「五月蠅いってなにさ! ……でも、本当に大丈夫? 顔色、悪いように見えるけど」
「だから何でも無いって言っているだろ? きみはさっき言ったことですら覚えられないほど間抜けだったわけ?」
「別にそこまで記憶力が悪いわけじゃないけど、そこまで言うなら大丈夫なんだね?」
「ああ、そうだよ」
ずきずき、ぐちゅぐちゅ。幻痛のはずなのにまるで抉られているように感じる、垂れているように感じ始めた血液を拭うと、ばれないように笑顔を浮かべてマスターから離れるのだった。
「くっそ……なにが、簡単なクエストだってんだ」
グサグサと、絶えず刺されるような痛み。毒もまわっているのか、視界がふらつき、思わず自分の部屋のベッドに倒れ込む。どうしてこんな状態になっているのにメディカルルームに行っていないのかと言われてしまえば、クエストが終わってダヴィンチに声をかけられる前に、有無を言わさずに自分にあてがわれている部屋に戻ったからだったのだ。
動けない。目を閉じることさえ億劫な現状に、発生した当初を強制的に思い起こされた。見えなければ、聞こえなければ、感じなければ。せめてそれだったらマシだったのだろうに。ため息の代わりに短い息を吐き出していると、ピッと扉から音がして、見慣れたオレンジが見えた。
「オベロン、やっぱり」
「……」
脳天気にマスターはベッドに潰れるように倒れ込んでいた俺に馬乗りになる。何でそんなことをする、何で、そんな顔をするんだ。短く息を吐きながら睨み付けるも、そんなことは気にしないと、目の前のマスターはさらに顔を近づけてくる。
「無理してたんでしょ。さっき解析してもらってね、宝具に対してのカウンターの呪いみたいなものを持ったエネミーがいたんだって」
「……で?」
「宝具を使ったのがオベロンだけだったから、心配で」
「ふぅん?」
「ちゃんと話を聞いて。……その呪いを解く方法なんだけどね、えっと」
「なんだよ」
「その、呪いはですね……魔力供給、と言いますか、……イメージとしては、マスターからの魔力を、呪いで汚染されているところに流せば、だんだんと浄化されるらしくて。……オベロンが傷口だと認識してるところに触れるか、それか……キスとかそれ以外でも良いから……粘膜接触すれば……効率が良いって」
だんだんと言葉が小さく、途切れ途切れになっていくマスターに苛立ちが高まる。大方ふざけたダヴィンチか、下世話なサーヴァントがマスターに余計なことを言って送りつけたのだろう。
魔力供給しなければオベロンが呪いを受けてそのまま消えてしまう。そうとでも思っているマスターは、あくまで真面目に俺に馬乗りになったまま、傷を探ったり、顔を真っ赤にしたりと忙しそうであった。
勘違いをしているマスターには悪いが、どちらをしなくても時間と共にボーダーから得られる魔力で回復はする。ただ、それでも幻痛なのかそれとも本当にできてしまった傷なのか、それらには苛まれ続けるし、そんな状態を望むほどの変態でもなかった。
「お、オベロン」
「……なに?」
「だるそうだね……その、いい?」
「……」
良いと言っても言わなくても、どっちにしろ今は自分の意志でほとんど動くことができない。それならいっそのこと好きにしてくれ。
諦めにも似た視線を向けると、立香はそのまま顔を近づけてきた。そして、呪いから解放された後。俺は、やられたらやり返すとばかりに立香に食らいつくのだった。