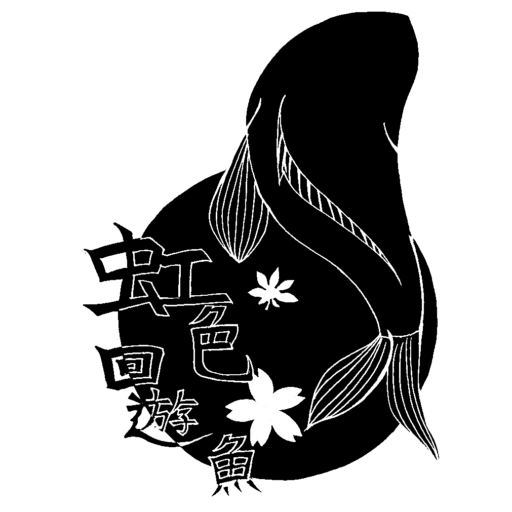73、響く音
「人理修復おめでとう、立香ちゃん」
「おめでとう」
「ありがとう」
辺りからおめでとうの声がかかる。その一つ一つにお礼を言いつつ、もう何年も一緒にいたような気になる方達と、祝賀を迎えていた。
「あ、オベロン! ここにいたんだ」
「やあ、マスター。こんなところまでご足労さま。どうしたんだい? 今日はめでたい日だろう?」
「そうだね」
「ずいぶんと慌てていたように見えるけれど、僕に何か用事があったのかな?」
「用事ってわけじゃないけど、ほら、もうすぐ退去だって話だったから、オベロンにも直接お礼が言いたくて」
「ふむ、そうだったのか。でも僕はもう十分にお礼はもらってるつもりだけどな。僕のために聖杯とか、沢山用意してくれたじゃあないか」
「まあ確かに用意はしたけど……」
人理修復中に手に入れた十個の聖杯。その全てをオベロンに手渡していた。オベロンは優しい笑顔でありがとうと毎回言ってくれていたけれど、本当に心からお礼を言ってくれていたのだろうかと、ずっと気になっていたのだった。
まだティターニアさえ召喚できていない自分。オベロンを呼んだのは冬木の地であった。マシュの盾を一瞥して驚いた顔をしたオベロンであったけれど、自己紹介代わりに辺りにいるエネミーを一掃した彼。敵の骨の破片が顔を擦ったのだろう、頬から流れた血を腕で拭って少しだけしかめっ面になった彼を見て、ツキンと胸が何故か痛んだのであった。
恋は得ようと思って得るものではなく、落ちるものだ。誰かが言っていた。果たしてそれは本当だったのか。冬木で得た痛みは彼と過ごす打ちにズキズキとした大きな痛みに変わっていった。こんなことをしている暇ではないのに。気づきたくないのに。彼のことを大切に思うと共に、彼と一緒にこの旅を続けたいと、そう思ってしまう自分がいた。
「オベロンにずっと謝りたいことがあって」
「……なんだい?」
「ティターニアのこと。召喚できなくて、ごめんね」
「別に、気にしてはいないよ。僕には原典がある。けど彼女はシェイクスピアの物語に存在するだけの人物だ。英霊として存在できないのかもしれないだろう?」
「そうかもしれないけど、でも」
ジークフリートとクリームヒルト。シグルドにブリュンヒルデ。その他にも私には把握しきれていないけれど、同郷のサーヴァントや大切なものなのだと分かるような関係性にあるものたちを召喚していた。みんなが仲良く楽しそうに、愛おしいものと一緒に過ごせたらいいなと考えていた。
「でも、やっぱり最後まで挑戦してみたいなって思って」
「それは、僕を思ってなのかな?」
「そうだね」
「それだったら、今はいいよ。僕にはマスターがいるからね」
「……?」
言っている意味がよく分からなくて首をかしげる。何で、私がいるといらないのだろう。沢山のサーヴァントから別の名前で呼ばれることもあるけれど、オベロンのそれもつまりそういうことなのだろうか? 分からなくて、でも、胸がズキズキと痛むようで、無意識に唇の端を噛む。ああ、もしかして、やっぱり。私はオベロンのことが好きだし、ティターニアにはなりたくないんだ。それでもオベロンが望むなら、みんなが望むなら。
「はぁ……何か勘違いしていないかい? 僕は別にきみにティターニアになって欲しいだなんて言ってないだろ?」
「なんで、……って妖精眼!」
「そうだとも。僕は妖精だからね。……どこかの特異点で誰かが言ってなかったかな? 英霊としての生まれは第二の生と同じようなものと捉えているって」
「確かに言ってたよ?」
「僕も同じように捉えようと思ってね。ティターニアのことは勿論大切だ。だけど、」
きみのことも同じように大切にしたいっていえば分かるかな? 照れたように視線を逸らすオベロンに、顔が赤くなる。うそ、だ。そんなことを思いつつ、心は正直に、ツキンと、また響くのだった。