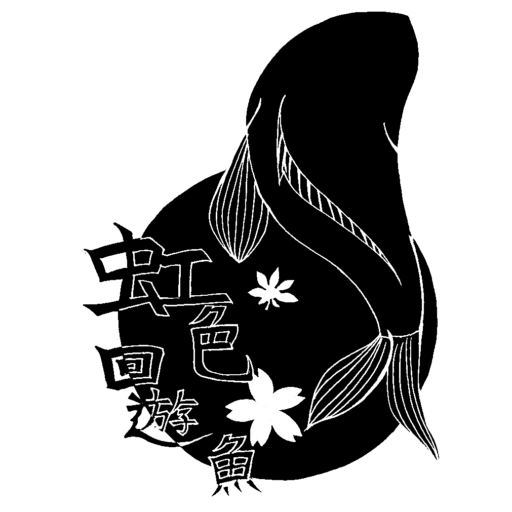79、普通の女の子がつけるもの
「我が妻よ。髪留めはどうしたのですか?」
「えっとね、切れちゃって。それに、この服には似合わないかなって思って」
「確かにシュシュがなくても我が妻はいつも美しいとは思いますが」
「あはは。美しいって……ありがとう。モルガン」
新しい礼装を纏って食堂へと向かうと、何人かに声をかけられる。礼装が新しくなったんだねだとか、その服も似合っているだとか。嬉しいことには嬉しいのだけれど、やっぱり落ち着かない。それは今までつけていたシュシュをつけなくなった事もあるけれど、それより何より首に残った跡のせい。何人かは気がついていた気がするけれど、気をつかってなのか触れないでくれているのが分かって、少しだけ恥ずかしくなった。
「オベロン……!さっきはよくも!」
「なんだい、マスター? 食堂に行ったんじゃなかったのかな?」
モルガンと話し終えた後、彼女にだけはばれていないかなとこっそりと伺いながらも、逃げるように食器をトレーに乗せて自分の部屋に戻った。そして、部屋の主より主らしい振る舞いをしている男に声をかけたのだった。
「こんなにされて、落ち着けるわけないでしょ!」
ベッドサイドのテーブルにトレーを乗せ、自分の髪の毛を触る。片側に髪を寄せると出てきた首元には、沢山の虫刺されのような跡。いわゆるキスマークというやつであった。
本当にどうしてこんなことになったのか。私とオベロンとは一応恋人同士という関係であるし、身体の関係も持っていることはある。それに同じベッドで眠っているけれど、それでも眠っているだけでこんなことをするのは流石に酷いのではないかと思った。
「流石にいたずらとしては酷すぎるよ」
「こんなことって?」
「キスマーク!」
「それは俺の虫の跡だろ?」
「確かにオベロンの虫には毒虫もいるけれど、こんなことしてないって言ってるもん」
してない。してないもん。そんな声が聞こえるような気がする。今まで虫妖精達とはちゃんと話せたことがなかったので、きっと幻聴なのだろう。それでも、それを信じないことはない。オベロンは笑っている。良い笑顔で笑っていたので、きっと嘘なのだ。
「とにかく、なんとかしてよ」
「なんとかって……増やせばいいわけ?」
「そんな訳無いでしょ! 本当にどうしてそうなるの? 頭どうにかしちゃったの?」
歪むにしてもオベロンらしくない。どうしたのだろうと考える。本当は自分の部屋の中なのでラフな格好をしたいけれど、跡は実は首だけではなく全身に残っていた。
「頭は別におかしくなってないけど? ……でもそれより、そうだな」
頭のてっぺんからつま先まで。じっとりと見られる。それから一旦目を閉じて、深く息を吸い込むように。そうして、オベロンが口を開いた。
「やっぱり今のきみにはシュシュは似合わないと俺は思うな」
「なんで?」
「妖精國の時から思っていたけど、シュシュをつけていられるような状況なわけ? 戦場で気をつかって」
口を噤む。どこかふてくされたような表情。言いたいことを言えないもどかしさ、と言うのだろうか。私は彼の呪いを思い出す。言葉は悪く取られたりねじ曲がったりする。言葉にせずとも行動しようとしたことで現実がねじ曲がってしまうこともある。彼の呪いは、彼をひねくれさせているのだった。
「戦場でおしゃれに気を遣うのは確かにすべきことではないよね。でも、きみはそういうことを言わないっていうのは分かってる。だから、違うことを言いたかったんじゃないかって思うんだけど、どう?」
「……」
「肯定とも否定とも取れる顔しないで欲しいな。……それで、オベロンが戦いについて話す。それ自体は関係のあることだと思うから」
考える。深く考えて彼の言いたいことを探し出す。そうして、もしかしてと一つの考えが浮かんだ。
「もしかしてさ、今って言葉が大切なのかな? 今の私には確かに似合わないかもね」
自慢では無いけれど、いつも髪につけているシュシュはカルデアに来る前からつけていたものだ。解れてしまったこともあったけれど、ダヴィンチちゃんはじめ、裁縫や物作りが得意なサーヴァント達が治してくれていたものだった。みんなと歩んできた歴史を刻んだもの。だけれど、カルデアに来る前の日常の象徴、それを思い出すものでもあった。
「似合わないわけ無いだろ」
「あれ? さっきと言ってること違うね?」
「ああ、だいぶ話すことが歪んでいるからね」
全くどっちなのだろうか。でもきっと、似合うし似合わないと思っているのだろうなと、正反対の彼の言葉から推測する。人理修復を行い、空想樹を切り倒していく自分。そして、カルデアを知らなかった頃の自分。
確かにシュシュは大切なものである。けれど、これからの戦いを考えるなら置いていった方が、元の自分を思い出すには良いのかもしれない。そこまで考えてはっとした。
「オベロン、もしかして……さ?」
「うん? それ以上は君の思い込みだろうから、言わないで欲しいな」
「そう?」
ふと考えたこと。それがもしかしたら正解なのかもしれないけれど、彼の性質からしても
絶対に言ってはもらえない言葉。それだったらせめて、今ぐらいは少しだけでも普通の女の子として彼に甘えてもいいのではないだろうか。
ベッドサイドにあったシュシュで髪を下に結び、寝転がっている彼に飛びかかる。嘘だろうと翅をバタバタとさせ、避けようとする彼に必死にしがみつくようにすると、諦めたように腕を回されるのだった。