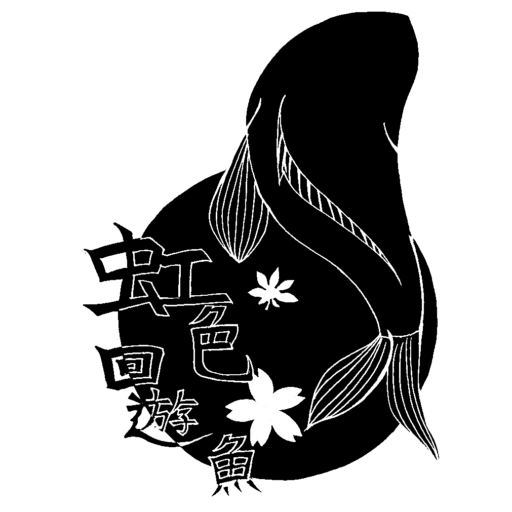100、愛してる
「おい、起きろ。起きろっての……バカ女」
「ぅう……ん……? おべ、ろん?」
「ああ、そうだよ。きみの彼氏のオベロンさ」
「うわっ、爽やか笑顔なのに怒ってるよね」
「そりゃね。何度揺すっても起きないし、いい加減起こすのにも飽きてきたところさ」
青い菱形が連なった髪飾りが似合う男。初めて会ったときは女の子みたいに綺麗な髪の毛だななんて思ったその髪の毛は、地毛が黒に近い灰色であったことを明かされた辺りから、つける髪飾りを変えて輝いていた。嗚呼、綺麗だなあ。黄昏色を反射させる窓をバックにこちらを揺すっていたオベロンの手が離れる。黒も似合うし、白も似合う。ふとそう思った。
「きみ、まだ寝ぼけてるね?」
「ぅーん? ねぼけては、いない、とおもう」
ふあっ、と出てきたあくびをかみ殺しながら口に当てた手を見た。右手の薬指にはオベロンの瞳を思わせるような深い闇を拾ったような石の着いた指輪が輝く。そういえばゲームセンターで頑張って取ってくれたんだよなと柔らかな気持ちになって思わず微笑みながら、寝ていたときの夢を思い出した。
過酷な人生を生きる夢だったかな。今日初めて行こうと思っている献血を受けた夢だった。献血を受けた後のお菓子を目当てに言っただけだった場所。気がついたらそこから飛行機に乗ってカルデアという組織で働くことになって、四十八人目のマスター、そして人類最後のマスターとして生きるのだった。そこでは沢山の英雄達と出会い、協力し、今の世界を終わらせようとする者達から聖杯を集めて……。
「すごく、長い夢を見てた気がするんだよね」
「夢?」
「そう。私が世界を救う夢。それから世界を」
壊していく夢。自分の世界のために他の世界を否定し、壊しながら進む夢。まるで滝行でもしているかのように、肩に、身体にのしかかる偽りと思われる記憶、想い。世界を壊しながらも目を背けずに進む自分。どうしてそこまで強く生きられるのか分からないけれど、突き進み、そうして彼と出会ったのだった。
「オベロン」
「……何?」
「帰ろう?」
「何処に?」
「カルデアに」
「……」
オベロンと出会った。一緒に旅をした。彼が自分の妃について語っていた記憶がある。奈落へ落ちていく彼を見た。これで良かったのだと思っていたけれど、なぜか再会してしまった。そして一緒に世界を救って欲しいと願い、同時に愛して欲しいと願ってしまったのだった。
「……、きみはさ、もう、世界を救う必要なんて無いんじゃないかな? 人類最後って言葉だってカドックがいるんだろ?」
「私の身体はどうなってるの?」
「はあ。俺と話をするつもりは無いようだね。分かった、特別に教えてやるよ。きみはカドックとマシュを庇って敵の攻撃を受けて、現在は集中治療を受けているとこさ」
「教えてくれてありがとう。それで、この場所は? 君が用意してくれたの?」
「きみの記憶の断片をつなぎ合わせたものさ。ここで死ぬまで生活していれば、俺は苦もせずにカルデアを崩壊させられる。良い判断だろ?」
「確かに夢に閉じ込めるのは良い判断だと思うけど、それって、オベロンが彼氏の必要あったわけ?」
「……」
「オベロンじゃ無くて適当な人でもあてがっておけば、私が記憶を取り戻しても、ここが夢だって思わないと思うんだよね」
本当に真面目で律儀で、それでいて心配性なひとなのだと思う。自分の目で見て、確かめて、それで真っ直ぐひとと向き合う。そんなひとなのだ。だからこそ好きになって、絶対に彼と最後まで一緒に過ごしたいと思ったのだけれど。
「もう一度言おうか。きみが世界を頑張って救う必要は無い。ここで余生を堕落して過ごしたとしても、別のマスターがきっと何もかも終わらせるだろうよ。それでも、きみは愚かにも進もうとしているのかい?」
「うん。自分でもどうかと思うところはあるけれど、それでも進みたいと思ってるよ。それにね、私はまだ君に言ってないことがあるから、帰らないといけないんだよね」
「おい」
オベロンが続く言葉を止めようとしてくる。まるでそれを聞いてしまったら自分の大切な部分が根底から覆されるような必死な声だ。だけれど、それでも私は続けた。
「私はね、オベロン。この優しい夢から目を覚まして、それでね? 君に『愛してる』って
言いたいんだ」
「……」
「どんなに辛くても、私の正義が間違っていても、それでも愛しているひとがいればそれでいいの。生きていこうって、先へ進みたいって思えるの。だから、お願い。帰して?」
「……、ああ、もう、きみはそんな人間だよな!!」
全く以て愛なんてものは理解できないし、幸せだって理解できない。ただただ、気持ちが悪いだけ。そんな俺にどうして。
分からないといった顔をしたオベロンが私の頬を両手で掴んでくる。それを受け入れ、目を閉じる。そうして目を覚ました。
「……」
痛い。少しだけ苦しい気がする。全身は包帯が覆っている。そして、そんな私が眠っている横で、何が面白いのかニヤリとした笑みを浮かべてこちらを見るオベロンがいたのだった。
「オベロン」
「なんだよ」
「その、ありがとう」
「それだけ?」
「じゃ、ないよ」
夢の中では言えたのに、言えないわけ? そんな風に煽ろうとしているような顔。それでも私を心配してなのか、あまり騒がしくはしないようにしてくれている。それとも話した事による呪いを心配しているのだろうか。珍しくおとなしくしているオベロンに私は口を開いた。
「ねえ、オベロン」