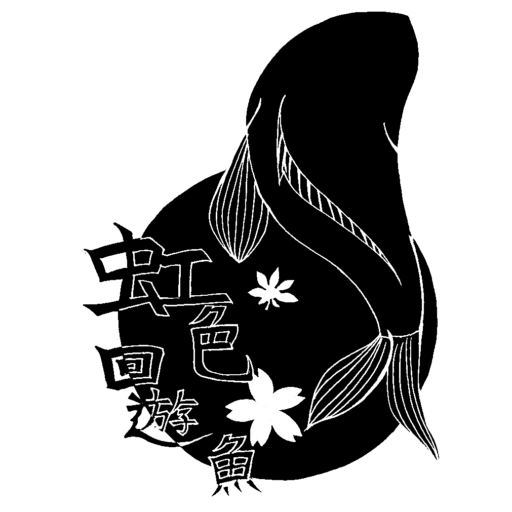「ぁっ……ぅ、ん、ひゃぁ!」
「……ん、」
ああまた今夜もだ。アルトリア・キャスターは深夜に始まった男女の運動会の音を耳に入れないように枕で両耳を押さえる。けれども毎日こびりつくように流される喘ぎ声と言う名のBGMに、それを覚えてしまった体は熱くなるばかり。今日こそそれに流されるわけにいかないと、しっかりと耳を押さえようとした。なぜなら……。
「ゃ、あ……ォベロン」
「はっ、……リツカ!」
アルトリアにとってとても大切な、幼馴染であるオベロンと立香が致している声が漏れ聞こえているから。
小さいころからこの二人は両片思いをしているなと思うことがあった。それは小学校でオベロンが立香のことをわざとひどい言葉で罵っていたり、中学校の頃に、バレンタインを幼馴染とはいえ渡し続けるのはおかしいよね、と悩まし気に立香が言っていた時だったり、はたまた高校でオベロンが告白されているのを遠くから立香が見ていたり、その後相手を振ったオベロンが、立香がいただろう方を何とも言えない顔で見ていたり。
どちらかを性的な意味を含めて好きだとかそんなことはない。アルトリアはそう思っている。あえていうのであれば二人とも好き。これが彼女にとって解である。そんな好きな二人が幸せであるならばどんなにうれしいことか。そう思う心もあるけれど、連日立香に無理をさせすぎなのでは?と、壁殴り代行よろしく壁でも殴ってしまおうかと考えたくもなる頻度で、オベロンは立香の部屋に通って、お付き合いをしている男女の夜の営みを行っていた。
男性の性的欲求が高まるのは十八がピークでしたっけ。ふと好奇心から調べた掲示板に載っていた情報を思い出す。それを考えれば、今年でちょうど十八を迎える三人の中で、オベロンが一番性欲があるってことなんでしょうかね。って私ってば何を考えて。頭に浮かんだ卑猥な妄想を一瞬で霧散させるも、その頭に、耳に、新鮮な喘ぎ声が入る。
幸い立香の部屋は角部屋で、その隣にアルトリア・キャスター、そしてその隣にオベロンが住んでいるという構図になっている。オベロンのさらに隣にも他の学生が住んでいるので、必然的に三人で集まるとしたら立香の部屋になるのだけれど、だからって。だからって毎晩二人でそんなエッチな事ばかりしていたら、成績だって下がってしまいますし、そうしたらこのアパートからも追い出されてしまいますよ。アルトリアはもう一度聞かなかったことにして、赤くなってしまった耳を塞ぎ、足をもじもじとさせながらも耐えようとする。
このアパートはいわゆる学生寮に近いものである。ただし、恋愛自由、男女も区別なしに同じアパート区画に入れて、家賃も格安。だからと言ってボロアパートではない。こんなに良い場所であったなら、さぞ倍率も高いのだろうと思われるかもしれないが、但し書きとして。成績上位十五位以内に入ること。これがこのアパートに住む条件となっていた。先月も十五ぐらいをギリギリ保っていた生徒が圏外になってしまい、泣きながら荷物をまとめていたのを見送った。それなのに、オベロンときたら。毎日立香を鳴かせて。学校では授業中に眠りそうになっていたら、足を蹴飛ばして起こすだなんてひどいことをしているのであった。けれども、そんな二人の声を聞いている自分だって。
気のせいだ。アルトリアはそう思いながらも、恒例となってしまっている確認を行う。生理が来ていないかの確認です、と、足の間に手をそろりと伸ばす。くちゅりと手に触れた液体を、茶色の豆電球のみついている室内の光にかざす。血ではない。それだけわかれば、ほら、手を拭いて、それで寝てしまいましょう。すぐ横にあるティッシュボックスに手を伸ばせばそれでいいのに。アルトリアの手はもう一度足の付け根に向かい、もう片方の手は彼女の胸へと向かう。
「……っ!んっ……」
最低だ。今日もアルトリア・キャスターは罪悪感に晒されながら、片手でパジャマのボタンをはずしつつ、もう片方はパンツの中、大切なところへと伸ばす。決してオベロンで想像しているわけではないけれど、立香の部屋へ遊びに行ったときにたまたま見つけてしまったコンドームの箱を思い出してから、毎日のように響く声を猫の喧嘩ではないと理解してからこうなってしまっていたのだった。
膣口にそっと指を沈め、壁をこするように抜き差しをする。胸に伸ばしていた手は、小ぶりのブラジャーをめくって、焦らすように、中心には触れないように、円を描いて周りへと触れていく。気持ちいい。二人の息遣いに耳をそばだてて聴いているだけで、二人がしていることを想像するだけで、気が狂いそうになるほどに、自分の身体も慰めてしまいたくなる。それほどに二人が深い仲であることに興奮が収まらない自分は変態なんじゃないかと思いつつ、指の本数を増やす。そうしてもう声を我慢することすら忘れて、口から洩れる音をそのままに、ただ果てることだけを考え始めた、その時。
コンコンコンとノックが聞こえた。最初は三回。次に二回。それから三回。それは三人で決めた合図であった。このアパートには共用のオートロック部分以外に相手の顔が分かるものがない。なので共用部分を過ぎた居住区に入ってからも相手が誰だかわかるように、親しい相手との区別のためのノックの合図が生まれていた。そして、先ほどの合図はオベロンか立香が使うもの。アルトリアは、どうして……と思いつつも、ウェットティッシュで手を拭いた後、急いで服の乱れを直して玄関に向かう。
「はっ、はい。申し訳あり」
「ごめん、キャストリア」
「リツカ?」
申し訳ありません、寝ていたもので。こんな言い訳は抱き着いてきた立香にさえぎられる。それからどうしたのだろうと驚きつつ、立香の背後に立っていたオベロンを見る。
「ど、どうしたのですか?」
「どうもこうも、こいつが言い出したんだ。キャストリアが寂しがってないかって」
「寂しがってる?」
「きみ、俺たちが……、今日も一人でさっきまでシてただろう?それのことだよ」
「ぁっ……」
「俺たちが付き合ってから一人にしちゃうことが多いから寂しがってたりしないかな? ってリツカがいうものだから、俺も考えたってわけ」
「な、なにをです?」
とりあえずそんな話は部屋に入ってからの方がいいだろうと思い、アルトリアは二人を部屋に通した。立香は抱き着くのをアルトリアの腕に変えて、オベロンはその後ろをついていく。それから三人で部屋の真ん中の丸テーブルを囲むような形で座った。
「今日はどうして最中にって思わなかったわけ?」
「それはちょっと思いましたけど」
こちらの幼馴染に嘘は通じない。自分もだけれど、オベロンも。昔から人のつく嘘には敏感で、ごまかしも分かってしまうのであった。なので今さら嘘や隠し立てをしても仕方がないと思い。受け入れたままに答える。
「今も聞こえてるだろ?」
「えっ?」
壁に耳を当て、聞いてみると今も確かに聞こえる。ちょうどクライマックスに向かっているところだろう、二人とも互いの名前を呼んでいるだけで、あとは意味をなさない音の羅列が……が?
「ようやく気付いたってわけ?」
「オベロン、最低です!変態ですか、あなたは?」
「幼馴染オカズにオナってるやつに言われたくないんだけどな、その言葉」
「ぐぬぬ、返す言葉がありません」
遠隔操作のボタンで音量を上げ下げしながらにやつくオベロン。それを見て顔を真っ赤にしながらうつむく立香。それからアルトリア。オベロンは今日のために自分たちの情事の音を録音、編集していたのだった。どうしてこんな変態男を立香は好きになったんだと思いつつ、アルトリアはオベロンに言葉を続ける。
「それで、考えていたこととは?」
「リツカが『キャストリアがさみしいのは嫌』って言うんだったら、いっそのこと三人でセックスするのはどうだい?って」
「あなたほんとうにバカなのでは?」
立香のために身を引いたことはないし、そんなことを二人はさせないと分かっているけれど、それとこれとは話が別で。私だってセックスは好きな人と、好きな人、と?
「ようやく分かってくれたようで何より」
「オベロン、その顔はムカつきます」
「そう?リツカは俺のこの顔も好きだっていってくれたんだけどなぁ?」
「リツカ、やっぱりこの男とはすぐ別れるべきです。それで私と付き合うべきかと」
「つれないこと言うなよ。俺だって、二人のことは気に入ってるんだ」
「わ、私もオベロンのこともキャストリアのことも好き、だから……もしキャストリアさえよければ、寂しくはさせたくないなって」
「それは……」
私だって二人のことは好きだ。そうアルトリアは思っている。それは友愛だとも。けれど、性的な目で二人を見ていることも、そういう目で二人のことが好きなことも本当は事実であって。どちらかが欠けることも、自分が抜けることも嫌な事であった。
「わかりました」
絶対にそう返事をすることを分かっていたでしょう、とアルトリアはオベロンを軽く睨みつける。オベロンは睨まれていることに気づきながら鼻で笑いつつ、立香を抱きしめて、アルトリアの前で口づけを落としてから、挑戦的に腕を広げるのだった。