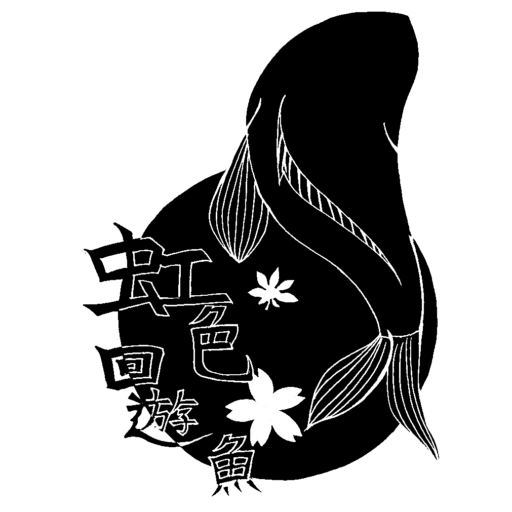使用人の朝は早い。日が完全に上りきる前に目覚めたら、まずは朝のミーティング、予定確認。それから朝食の準備を行い、ご当主様を起こしてからの食事の配膳。自分の食事はご当主様が食事をされてからか、起床前に行うかだ。
さて今日の予定は、と屋敷入り口の階段を下りたところで足を止めるとどこからか感じる煙草の渋い香りに顔をしかめる。誰のものかが分かっていたし、相手も私がこのまま近づいてくるのを分かっているからこそ、そこでタバコをふかしているのだ。階段裏のいつもの場所。そこに足を運ぶと、濃い柑子色の髪を持つ青年が床にしゃがんでいた。
「やあお嬢さん。もしかして、俺に会いに来てくれたんで?」
「冗談はよしてよ、ロビン。私なんか口説いても面白くないでしょ」
「いやいや、リツカもお年頃ですし、俺からみたら十分魅力的に、と。今日はそんなことじゃなくてですね、坊っちゃんはいらっしゃいます」
「シャルルのこと。それだったら今は食事に」
「はあ。そうですかい。坊っちゃんはこの時間は優雅にお食事ねえ。まあいいですが、伝言をお願いしたいんですわ」
「いいけど、なんて」
「例の縁談の件、今日の午後とのことで」
「縁談?」
「あれ、聞いてないんですか。隣町のお嬢さんとので、何でも事情があって断れないから会うだけでもってなっていまして」
てっきり知っていて認めているとばかり思っていましたか、違ったんですかね。煙草の火を消し、立ち上がりながらロビンは答える。
「知らされてなかったと思ったけど、ってロビン。認めているって何を」
「え。いやてっきりリツカは坊っちゃんのこと、す」
「わああ、ちょっと待って。それは、そう、だけど、けど認めるのもなにも私はシャルルの何でもないから」
「でも坊っちゃんに迫られているんでしょ?この間も朝から熱烈に口説かれていませんでしたっけ」
「うう、確かに覚えはあるけど。て、そうじゃなくて、縁談だったらこちらでもなにか準備をしないとダメなんじゃ」
「それは」
「それは大丈夫ですよ、リツカ」
「シャルル」
「二人が話していたことが気になってしまってね、すまない」
二階から降りてくると、すぐ階段裏、私たちが話していた場所まで近づいてくると、最初の私のように顔をしかめる。
「ロビン、またこんなところでタバコを吸っていたのかい。屋敷に臭いがついてしまうし、リツカの前でもあるのだからと、毎回いっているだろう」
「へいへい、坊っちゃんの話は耳にタコができるぐらい聞いていますよ」
「だったら」
「ストップ、ストップ。私は大丈夫だから、ね。シャルルも今日は、その、することがあるみたいだし、ロビンも伝言を伝えたらおじさまから帰って家業を手伝うようにって言われるんでしょ」
このまま二人きりにするといつまでも喧嘩をし続けるので、止めようとする。二人を喧嘩させるなどメイドとして失格だし、自分の仕事を放り出してまで二人を眺めている時間もない。縁談のこともある。きっとシャルルは私に縁談のことを知られたくなかったのだろうけれど、知ってしまったならそれを無視することもできない。
ほらほら、と二人を引き剥がしてシャルルの背を押して彼の部屋に押し込む。少し乱暴だったかと思いながらも彼を伺うと、なにかを思案しているようだった。
美しく整備されたシークレットガーデン。目の前には可憐な少女が微笑んでいる。しかし、僕からしたらそんな事はどうでもいいことであった。早くこの空間から抜け出して立香の作るおやつを食べたい。そんなことを考えていると彼女が声をかけてくる。
「久しぶりね、サンソン」
「ええ、お久しぶりです。マリー」
「ふふ、あなた、相変わらず変わりがないのね」
「変わり、とは」
「真面目で誠実なところだとか、それだけじゃないわ。あなた、昔からあの子のことばかり見ていたものね」
「そうでしょうか」
「ええ。だから私もあなたみたいに誰かを愛したいって思えたのですもの」
彼女はマリーアントワネット。隣町の一番の貴族であり、僕の父の友人を父親にもつ女の子で、所謂幼馴染のような関係だ。その他にも幼い頃からの知り合いとしてはロビンフッドやリツカもいるが、僕の素性を知っても付き合いのあるうちの一人が彼女であった。
「誰か、ですか」
「ええ、だから今回の縁談も私のお父様が決めてくださったことだけれど、お断りしようと思っているの」
「ええ」
「だって、ここで婚約になったりしたら私もあなたも、それだけじゃないわ。みんなが不幸になってしまうと思うの」
「そう、ですね。僕も……それに彼女も」
幸せに、なっても良いのでしょうか。彼女が僕との幸せを望んでくれるのでしょうか、そう言おうとしたときにがさりとマリーの後ろの茂みが動く。
「えいやっ………!」
「えっと、リツカ?」
「あらあら、まあまあ」
お久しぶりね、と続けられた声に唖然とする立香。片手には箒を逆さに持って、まさに降りかかろうとするような体勢をとっていたので思わずマリーを庇うと、悲しそうに目を伏せる。
「リツカも久しぶりね」
「そう、ですね。今日に縁談の相手はマリーちゃんだったんだ」
「ええ、そうよ。父がね、私たちが生まれた辺りから決めていた縁談みたいで、どうしても会うことだけは断れなかったの。でも心配しなくていいのよ。私、この縁談を断るつもりだったのだもの」
「え?」
「だって、こんなに愛し合っている二人を引き離すことなんてできませんわ。それに私だって、思う殿方ぐらいはいてよ」
「マリー、それは聞いてないのだが」
「あら。サンソンには言っていなかったかしら。ルイって言ってね。とても愛情深い方なのよ」
私を一番に愛してくれるだけじゃなくて、自分の周りのすべてを愛せるような素晴らしい人なの。と続けるマリーの声は幸せで溢れている。
折角だから今度は四人でお茶でもいかがかしら。でも、それよりも今は二人で話し合った方がいいかもしれないわね。そう言うと、マリーは座っていた席から立ち上がって、シークレットガーデンの出入り口へと足を向けたので、思わず駆け寄る。
「お父様には、私とは価値観が合いそうにありませんでした。やっぱりこれからも友達としてお付き合いをさせてくださる、って聞いておくわね」
「あ、ああ」
「サンソン。立香とお話ししなきゃダメよ」
最後は自分にだけ聞こえる声量で話す。そのまま彼女がいなくなり、二人きりになった。僕は振り上げていた箒を下ろしてへなへなと座り込む立香に近づく。立香は箒を支えにして真っ赤になった顔を隠しもしないで混乱しているようだった。
「リツカ。いくつか聞いてもいいですか?」
「え、あ、ぅ」
顔をあげて少し怯えたように声を絞り出す。彼女の瞳に映った僕の顔は真面目な顔をしていた。
「なぜ、マリーに向けて箒を振り上げたんだい?」
「そ、それは」
「何があっても人に危害を加えてはいけない、そうですよね」
「はい」
「でも、リツカは理由なくそんなことをするような人ではない。ですから、どうしてそんなことをしたのかと聞きたいのです」
怒ってはいないですから、聞かせてくれませんか。そう問うと、ゆっくりと話し始める。
「今までシャルルは、全部の縁談を断っていたから。きっと今回も本当は断りたかったんだろうなって思って。ごめんなさい」
「ええ、でもそれだけではないのでしょう」
「え、どうして」
唇の端を噛み続けていた彼女のそこに指を触れさせる。
「リツカはなにかを隠したり嘘をついているときなどは、視線を世話しなく動かしたり、唇を噛んだりするからね。あまり癖にすると痛んでしまうから、気を付けた方がいいと思いますよ」
「気を付ける」
「ええ。それで?」
「私は、シャルルに幸せになってほしくて、結婚は幸せなことだって思ってて、でも、私にいつも優しくしてくれるけど、私はただの使用人だから。えっと、シャルルには幸せになって欲しいけど、私じゃ身分不相応だから、私が不祥事を起こせばシャルルから離れて暮らせて、それで、シャルルは別の人と幸せになれるのかなって」
色々な意味で思わず脱力するが、無理やりにでも力を振り絞り、彼女を抱き締める。
「はぁ。全く、そんなことを考えていたのですね」
「う、うん」
「まず始めに言わせてください。僕はリツカのことを愛しています。それこそ幼い頃、僕が初めてサンソン家の仕事に手を出したときがあったでしょう。あの雨の日からですよ。雷の一撃にあったようだなんて言葉は使いません。あの時から僕の心は君で満たされているのです。僕の家の表だっての仕事は貴族として過ごすことですが、裏家業は知っている通り処刑を生業としているものです」
「うん」
「それでも、それを知って、実際に携わっている現場に出くわしたのに、リツカはいつものリツカで。あんなに汚れた僕を、ずぶ濡れのままじゃダメじゃないと叱ってくれて、僕を僕のまま、シャルル=アンリとして見てくれたんです。僕からしたらそれがどれだけ嬉しいことだったか」
「そんなこと」
制する彼女の顔を覗きこんで言葉を続ける。
「そんなことでもです。それで、リツカ。僕は改めて、貴女に求婚をしたいのですが、受けてくれますか?」
「ここで、はい以外の言葉ってあるかな。勿論、私で良ければ。ふつつかものですがよろしくお願いします」
「良かった。必ず、僕が幸せにします。誰にももう譲りません。そうですね。まずはロビンが屋敷に自由に出入りするのを禁止しましょうか」
「え、何で」
「ところ構わずリツカを口説いているからですよ。本気じゃないのがたちが悪い。いえ、彼が本気で口説いていたとしても不快ですが。……ともかく、もうリツカには僕がいるのですから、彼がリツカに近づかないように」
言葉を続けようとするも、立香が僕に口づけを贈ってくる。
「もう、シャルルだって分かっているでしょ。シャルルにとってロビンのことも大切な友達だって。それにロビンがいなきゃ、お仕事とかどうするの」
「ですが」
「それに、私だってシャルルのことが好きだったんだから、ロビンに靡いたりしないよ?」
「全く、リツカには敵いませんね」
「ふふ、私だってシャルルのことが好きだもの。それに、夫婦ってお互いの駄目だと思うところも二人で話し合って改善していくものでしょ」
「そうですね」
もう一度、と顔を寄せて拙い口づけを受ける。それは晴れた満開の薔薇が咲く午後であった。