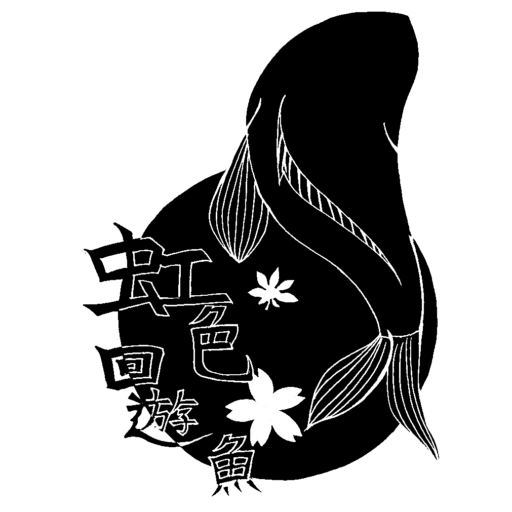はあはあ、と荒い息が部屋の中を満たした。三十分以上も押し付け続けられた腰が引かれると、収まりきらなかったものが息を吐き出す度にこぼれ出す。その熱さと居心地の悪さは理性を取り戻させたが、目の前の彼はその光景にごくりと息を飲み、再び覆い被さってくる。もう限界だからと慌てて彼の腕を叩くけれど伝わらずに、抱き締められて、首に口づけを受け、肌が泡立つような欲情を感じはじめる。取り戻した正気はすぐにどこかに隠れて、もっと肌を合わせたい。抱いてほしい。彼に貫かれてしまいたい。いっそ壊されるぐらい激しく攻め立てられて、彼の子を身に宿したい。そんな浅ましい欲望が頭をもたげる。目の前の熱を持った氷のような瞳を持つ彼もそれに気がついたようで、目を細めて怪しげに微笑んだ。そしてそのまま、胸、腰骨、内太ももと唇を落としていき。
Ω特有の発情期が起きる数ヵ月に一回のその時。抑制剤の在庫も限られているカルデアでの対応は難しいけれど、何とか君の分だけは確保しよう。そう言いつつも唸るダ・ヴィンチ女史に対して、何がですか、と聞いたのは藤丸立香のバースがΩであると判明したときであった。彼女の両親は、二次性徴のころに行われるバース検査の結果を彼女に伝えることなく、それどころか、男女性以外にも性があることを伝えていなかった。また、彼女自身も性的なことに対して関心が薄かったことから、なにも知らずに育っていたのだった。
最初の特異点を修復しているときには良かったが、抑制剤には限りがある。第四特異点に進むころには、カルデアという慣れない場所で人理修復という大を成すストレスによって発情期の周期が狂ったこともあり、抑制剤のほとんどがなくなってしまっていた。抑制剤がなければ、番もいない藤丸立香は周期的にαを求めるだけの獣のような姿になることは分かっていた。運悪くそこに無体を働くようなαが現れたら。そう立香自身も職員も頭を悩ませていた。職員たちはほとんどがβクラスであったが、立香によって召喚されたサーヴァントは英霊ということもあり、ほとんどがαである。
「うーん、まだ観測されている特異点、それから未観測の特異点がいくつかある可能性も考えると薬もなくなってしまう可能性が大きいと思うのだけれど何か対策はあるかな、サンソンくん」
「いえ。私含め医療班で対策を考えておりますが、未だに方法を見つけることができてはいない、というのが現状です。しかし、何故僕個人にお話を?」
カルデア内医務室。かの天才ダヴィンチは人払いをしてサンソンと会話をしていた。立香がΩであることは立香本人、サンソンとナイチンゲール、そして一部医療を任されているサーヴァントを含めた医療スタッフと、カルデア最高責任者代理のロマニ・アーキマン、レオナルド・ダヴィンチ。彼らのみが認識している事項であった。医療に関してのみの事柄であればわざわざ人払いなどさせない。自分でなければならない何かの理由があるのだろう。そうサンソンは考える。
「流石サンソン君。きみにはわかってしまったか」
と、目の前のダヴィンチは、口調とは裏腹に真剣な顔で向き直った。
「こう言ったことは単刀直入に言った方がいいだろう。サンソン君、君に頼みたいことがあるのだよ。君のマスターである藤丸立香を、発情期の時に抱いてほしいんだ」
「なっ、正気なのですか?」
「もちろん、君が怒ることを見越せるぐらいには正気さ。それに、この話は立香君自身から提案があったことなんだよ。『このままだと特異点を修復するまでに抑制剤のストックが足りなくなる。それだったら、魔力供給のこともあるし、誰かに抱いてもらうことも考えないとダメ、かな』ってね」
「おおよそのことは理解できまし。しかし、何故。あなたなら止めることもできたはずだ」
「もちろん止めはしたさ。それでも彼女の意志は硬かった。それに君の考える通り、今とれる策がないことも事実。私だって、方法があるならこんなことを彼女に受け入れてほしくはないのだよ。だからこそ、医学の心得があり、彼女のことを誰よりも大切に扱ってくれるだろう君に話している。そのことだけは理解してくれたまえ」
目を伏せて話すダヴィンチの拳は固く握られっており、圧力が強すぎたのか、それとも爪で傷つけられたのか一筋の赤が隙間から零れる。サンソンは手当てをと準備をしつつも、考えてみるので少し時間をもらいたいと言って別れることとなった。
立香の発情期数日前。サンソンの部屋には何重にも魔術で壁や扉を破壊されないように施され、理性が無いうちには出られないようにダイヤルロック式のカギが内扉外扉共につけられた。さらに有事の際などにはお互いが連絡できるように対魔術用のトランシーバー、ダヴィンチ開発の番防止用ネックコルセットと、対サーヴァント――サンソン用の、非常事態に行動抑制の効果がある首輪がベッドの上に並べられている。ダイヤルロックは既に施されており、十分な食料も保存スペースに置かれていた。
「サンソン、ごめんね。こんなことに巻き込んで」
軽くため息をつきながら、自分用にと用意された首輪をつけようとしていると、シャワー室から室内着を着た立香が現れる。午後九時を過ぎて、小さな鞄一つを荷物に部屋にやってきた立香は、緊張して青ざめたような顔をしていた。サンソンは彼女の性格からも、そんなことは一切したことがないのだろうことは予測できたので、リラックスできるようにと入浴を薦めていたのだった。
「いえ、マスターが気にすることではありませんよ。それより、部屋に来た時より顔色は良くなっているようですが、もう、大丈夫ですか?」
うん、とうなずく立香にネックコルセットを渡して自分でつけるように促す。扉と同じくダイヤル式のカギが付いているそれは、サンソンが外さないようにと、仕様を立香にしか教えられていない。サンソンから背を向けた立香はカチカチといくつかの部分をいじり始める。そのまま首に硬質な布を巻いて鍵を閉めていく。一瞬だけさらされた首は 紅潮しており、それが湯上りという訳なだけでなく、性的な意味からの興奮より起こっていることが分かった。彼女自身の体から漂う甘い香りも相まって、頭に霞がかかるような感覚を起こす。そのままぼんやりとした頭で、誘われるようにコルセットをつけ終わった彼女に近づいた。
「あっ、ぅぁ、んぅぁああ!」
ガクガクと震えながら弛緩する体を抱き締めて、奥へと穿つ。気を失ってしまった立香であったが、体内はサンソンの子種が欲しいと強請るように締め付ける。サーヴァントは性交を行ったところで妊娠することはないと理解していることもあり、促されるままに最奥までぐりぐりと押し付けて精を吐き出す。押し付けた拍子に人間であったころにはなかったはずのそれが彼女の中に潜りこむ。長い間緩い快感と、そのままの状態の射精が続くことは分かっていたので、気絶している立香を起こさないようにしつつ、時計と彼女の体の様子を見る。最後に時計を見た時から1週間がたっていて、立香の身体から感じていた甘い香りも薄くなっている。発情期ももうじき終わるのだろう。立香の体には無数の噛み跡と鬱血痕、肘や膝はこすれてできただろう傷がいくつもできていた。気絶する直前に吐き出していた喘ぎ声は苦しそうで、しゃがれていた。
ベッドサイドに置かれた救急箱に手を伸ばそうとしたサンソンは腰の痛みに顔をしかめて、自身の治療に特化した魔術を為した。サーヴァントに効果のある魔術ではあったが、立香に使っても何一つ効くことがない。彼女自身を治療するには魔術を使用しない一般的な治療をしなければならない。未だに震える足に喝を入れつつ、繋がったまま処置を施す。性行為に溺れていたときには気づかなかったが、治療を行うとつい先程ついた傷だけではなく、特異点でできたであろう傷の後が目に付く。傷自体はすでに治っていたけれど、多数の傷跡が服に隠れる場所についていた。
発情期が来るたびに鍵のかかった部屋へ、二人きりで閉じ込められるように入る。その時の記憶はほとんどないけれど、覚えている限りでも、獣のように絡み合って奥を穿たれていること、ただただ気持ちがよいこと、それでも足りなくて彼を求めてしまったこと、それらを覚えていた。
ダヴィンチちゃんに相談したときに目ぼしいサーヴァントとして何人か挙げられていたけれど、その中のシャルル=アンリ・サンソンであれば、無体なことはされないだろうと確信があった。果たしてその確信は事実であったわけだけれども、藤丸立香の悩みは日々大きくなっていく。贅沢な悩みなのであろうが、彼がどういった気持ちで自分のことを抱いているのか、自分の存在が彼にとって煩わしいものになっていないか、そう考えてしまうのだった。発情期が終わり、理性を取り戻した立香が目を覚ますと、目の前には服をきっちりと着こんだ、又は着込んではいないものの、黒いコートを羽織ろうとしている後ろ姿をよく見ていた。自身の身体は、何度も交わりなんだかよくわからない液体でぐしゃぐしゃになっていた記憶とは裏腹に、シャワーを浴びた直後のような清潔感と、取り込まれたばかりのような柔らかさのある服を着込んでいる。僅かな体の痛みと腰のだるさ。この事から現実に抱かれていたことは理解していたけれど、お体の方は大丈夫ですか、と薄氷の瞳を持つ彼に、普段と代わり無い口調でそう言われると、まるで何事もなかったかのように感じてしまうのだ。シャルル=アンリ・サンソンはそうあるべきもの、自身に求められている役割のためであるならば、己の意思をも砕いて行動を起こすことのできるサーヴァントである。マスターからのオーダーであるなら、人殺しに関わること以外であれば何でも、自身の意思でないことであっても行うだろう。
「まあ、サンソンったら。でもマスターがそのことで悩んでいるだけだと知って安心したのよ」
「マリーちゃん、その、こんなこと聞かせちゃってごめんね。それで、安心って、どうしてかな」
「いえ、私だって子供を持ったこともある。それに恋の話っていつでも素敵でしょ?安心したといわれてマスターとしては複雑かもしれないけれど、レイシフトに関すること、私たちサーヴァントのことで悩んでいるだけではなくて、一人の女の子として悩んでいることに安心したのよ」
数刻前に廊下で溜息をついていた立香を見つけてお茶会へ誘ったのは、サンソンとも生前から関係を持つマリーアントワネットであった。マスターである立香がΩ性を、そしてサンソンがα性を持ち、発情期の期間に何が行われているかはカルデアにいるものであれば大体の人間そしてサーヴァントにとってすでに周知の事実となっていた。中にはサンソンと立香が恋仲だと思っている者も多かったが、普段から二人と付き合いがある一部のもの、そして王妃の目はごまかせずに、二人きりのお茶会を開いている状態である。
「恋だなんてそんなマリーちゃんが思ってるような関係じゃなくて、その、私の性がΩだからサンソンを利用しているだけ、だよ」
「マスター、いえ、リツカ、少し聞いてもよくて?貴女とサンソンの関係を一応知ってはいるわ。だけれど、リツカがどうしてサンソンを選んだのかを知りたいの」
「それは候補は何人かいたけれど、サンソンが一番信頼できたから、かな」
「そう、サンソンもマスターにそこまで思ってもらえるなんて素敵だわ。でも、マスターは信頼できる殿方になら抱かれてもいいと思っているのかしら」
「そんな」
「私の知っているサンソンもマスターも、損得勘定で身体を許すような人じゃないわ。それに、例えば私がΩでサンソンにそういった関係を持ち出したらどうかしら」
「私には、止められないよ。サンソンだったらマリーちゃんでも、同じようにするんじゃないかな」
「リツカは嫌ではなくて」
目の前のマリーは逃がさないというように微笑みかける。マリーアントワネットは十四歳でルイ・オーギュストのもとへと嫁いだ。恋も愛もまだ知るような年齢ではない彼女は彼女の祖国オーストリアとフランス国家のため身も心もすべて捧げたのだった。
「最初に愛がなくても良くなくて。マスターの国でも親の決めたお見合い結婚があるのでしょう。最初に番という枠組みを作って、そこから愛を深めていくのも一つの形だと思うわ」
「私は」
「もう、気持ちは決まっているのでしょう」
「こんな爛れた関係からでも、彼のことを思っても、好きになってもいいのかな」
「何が正しいとか、間違っているとかヒトはいつの時代でも決めたがるものよね。今の私でも何が正しかったのかなんてわからないわ。でも、リツカが後悔しない道を進んでほしいと思っているのよ」
「うん。マリーちゃん、その、ありがとう」
「ふふ。それにね、愛おしい私の国民(サンソン)には、何時で
も幸せになってもらいたいって、思っているのよ」
冗談ともつかない笑みを浮かべて目を伏せる。シミュレーターで作られた茶会の場。マリーの背後の窓から部屋の中に風が入り込んで彼女の銀糸をたおやかに揺らす。風にあおられたためか立香の背後の扉が小さく開いて閉じた。
「あら、マスター。少し見づらいけれど、頭の後ろの方に花弁が」
手を伸ばすマリーに立香は身をかがめる。テーブル越しであったものの立香の首の近くにマリーの顔が近づいた瞬間、立香のよく知った女性のものとは違う手が、彼女の首を覆った。
「マリー。いくら貴女でもマスターの許可もなしにそういったことをするのは見過ごせません」
そこにはいなかったはずのサンソンがいた。彼は険しい顔でマリーをにらみつけるように立っている。
「ふふ、貴方が私にそう言ってくることなんてめったにないから新鮮だわ」
「マリー僕はふざけているわけでは」
「サンソン、私はβよ。だから貴方が危惧していることはできないのよ」
焦った貴方なんて珍しいわね。ニコニコと微笑み続けるマリー。
サンソンはマリーが自身に対して笑顔を向けることが理解できない。彼女最後を執り行った自分にどうしてそのような笑顔を向けることができるのか、と元より彼女の笑顔が苦手であった。現在はそれだけではないのだけれど、レイシフトの関係で呼ばれているからと立香の手を引き、彼女の部屋へと戻るまでに時間はかからなかった。
「マスター、リツカ。よく聞いてください。貴女はたとえ僕であっても心を許してはいけません。貴女は僕にとっても、他のサーヴァントにとってもマスターであり、そうでなくても貴方はΩ性。マリーが戯れ噛みつこうとしましたが、もし彼女がαだったら、マスター自身が傷つくことになる」
「マリーだけじゃなくて、他の子も、誰だって、ここには害をなそうとする人なんて」
いないよ。そう口にしようとした立香に口づけを落としてそのままベッドに力技で押し倒す。筋力がDだからと言ってサンソンは男であり、サーヴァント。簡単にベッドに仰向けに倒れた立香の上に馬乗りになり、首元の飾りに手をかける。カチャカチャと音がした後に首元が開かれ、軽く歯をたてられた。
「甘い香りがしますね。今度の発情期も近いのかな。マスターはここを安全だと思っているようですが、この香りは誰であっても僕たちが英霊と呼ばれる存在だからかもしれませんが、とても惹き付けられる香りなのです」
言いながら甘噛みをする。食い込まない程度にかけた歯の隙間から漏れる息に首元がしっけ、そこを次の瞬間にはぬるりとした舌に撫でられ、顔の横で置かれた手の爪先で強く引っかかれる。
「たとえ親しい相手だとしても、この世界には優劣が付けられてしまう性があることを忘れてはいけない。Ω性を持つものは番となったαから捨てられると二度と番を持つことができない、以降発情期が来るたびに一人きりでいなくてはいけない、精神的にも過度な負担がかかる、そう文献で読んだことがあります」
マスターはそうなりたいのですか。ひっかいた後に再び絡めた手はそのままに、上体を起こされたことにより、視線を合わせる。立香から見たサンソンの瞳はいつも以上に冷たく感じられた。
「そうは、なりたくないよ」
「それでしたら、僕の話した通りにしていただきたい。僕はマスターが誰かと番になることは構わないと思っています。ですが、僕たちサーヴァントとそういった関係になるのだけは反対です」
「それは、いつか君たちが消えちゃう存在だからかな」
「ええ、そうです。君は人間だ。人間として同じ人間と幸せになってほしいのです。僕たちはここに偽りの肉体を持って存在していますが、過去に生きていたものだ」
「サーヴァントとは幸せになれない、サンソンはそういいたいのかな」
「ええ。どうして今を生きていない存在と、幸せになれるのでしょうか」
サンソンはそういって立香と合っていた視線をそらせると、身を起こす。以前であったならその距離を詰められたかもしれなかったが、サンソンに向けていた淡い思いを自覚したばかりの立香には詰められず。そのまま部屋を出ようとするサンソンをただベッドの上で見つめていた。
自分でも立香に対してひどいことをしていると気が付いていた。人類最後のマスターだから、マスターが通常の生活を送り続けるため、そう理由をつけて立香を抱き続けている。ダヴィンチ女史からの提案を受け入れたときには、彼女を守るためだと、心など関係ないと考えていたが、自分の肉体年齢と変わらない小さな命に情が移るのは当然のことであって。おそらく立香を好ましいと思ってしまう感情を持つだろうと、はたまた最初から思っていたことを見抜いていた天才を思い起こし溜息をつきつつ、眠っている立香を見つめる。理性を取り戻して目を覚ました先にある、夕日色の髪の毛を梳く穏やかな時間が、いつの間にかサンソンにとって好ましいものとなっていた。
立香を起こさないように手を伸ばしてそっと流れのままに撫で付けながら、サーヴァントとマスターでは幸せになれないという、自身に対しても釘を指すために放った言葉を思いだす。今リツカと関係を持ったとしても人理修復が行われれば座へと還されることになるのだから、情を抱くことはリツカ自身を傷つけてしまう。それであるならばこんな思いを持っている自分から彼女を遠ざけるべきなのでは、という考えもサンソンは持ち合わせていた。彼はなにかを求めることを諦める、そういったことには生前のこともあり慣れてしまっていた。処刑人の一族であるということで冷めた視線を向けられ、学び舎を追われ、医者として頼られる一方恐れられて人に避けられ続けけた人生。愛していた人と一生を添い遂げることができたということは幸せなことであったが、何かを望むことを許される土壌に彼は育っていなかった。
「ん。さ、そん」
小さく身じろぐ身体に、完全に目が覚めてしまう前に体を清めようと霊衣を纏いながら布を手に取る。自分が無意識のうちに付けたであろう背中のいくつもの痕に目をそらしたいという気持ちを押さえながらふき終えて、シーツも取り替える。そのまま衣服を着せるためにと抱き上げると、体はほとんどなのも食べていなかったからか、何処かの特異点で抱き上げてエネミーから逃げ出した時より軽かった。
「おはようございます、マスター。体の方は大丈夫ですか?」
「ん、おは、よう。腰は、午前いっぱい休めば大丈夫そうだけど鞄に入っている飴をもらってもいい?」
「ええ、勿論。水と食事の方も持ってきましょう」
意識して平坦な声をしつつ、立香の服を整え、そのまま立ち上がろうとする。そこで、引かれる袖に気が付く。
「マスター、いかがなさいました?」
「あ、えっとその」
「食堂へ行ったらすぐに戻ります。まだ発情期も終わったばかりの貴方を一人にはできませんから、大丈夫ですよ」
立香が引き留めるように服の裾を掴む。だがサンソンはそれに気がつかないふりをして、念のためにとα用の抑制剤を打ち込んでから立ち去った。
「ねえサンソン。あなたはマスターのこと、リツカのことが好きなのかしら」
そう目の前で微笑んでいるのはマリーであって。傍から見たら決して相いれないであろう二人が誰も招かずにお茶会を開いていることにおかしさを感じる。
「マスターとの仲は最近どうかしら」
と、リツカの食事を用意していた僕に彼女が声をかけてきた。そして、いつの間にかお茶会の約束を取り付けられていたのだった。
「好き、とは。生前からでしょう、僕にとって君マリーアントワネットとルイ16世は敬愛の対象で、その気持ちは今でも。それに、愛は生前の妻に持ち合わせていたもの。では、マスターは、と問われると少々困ってしまいます」
「家族愛、友愛、親子愛、敬愛。世界にはたくさんの愛があるわよね」
「ええ、愛と呼ばれるものは語り切れないほどありますね」
「そのどれも、相手を大切だと思っているからこそ生まれて、行動になるものだと思うの。それで、サンソンはマスターのことをどんな風に大切に思っているのかと思ったのよ」
飲んでいた紅茶のカップから口を離して音をたてずにそっとテーブルに置くと、深い空色の瞳をこちらへ向ける。サンソンは彼女のその瞳に取り繕うことができずに口を動かす。
「僕は君よりもずっと前からマスターと共に人理修復の旅を共にしてきた。マスターはΩ性を持ちながらも自由な暮らしをしてきた、誰にでも手を差し伸べられる素晴らしい女性だと思っています」
「ええ、それはあなたたちを見ていてよくわかるわ。お互いを尊重し合っていて、認め合っている、そんなふうに見えているもの」
「彼女は僕にとっては、そうですね。例えるなら太陽な存在、というのでしょうか。僕にとって彼女は直視ができないほど眩しい存在で、触れてはいけないものだと、そう感じているのです。」
人間は太陽に焦がれて空を駆ける道具を作った。朝が来れば昇る暖かなそのぬくもりに感謝し、当たり前の存在としても捉えている。それはこの地球上にある全て、万物に与えられているもので、独占することはできない、してはならないものである。サンソンは、それでも太陽に焦がれていた。触れてはいけない彼女に触れて、彼女の大切なものを奪い続けている自覚はあったが、どこかほの暗い独占欲を満たされる感覚を得ていることも同時に思い至っていた。このような気持ちはマリーに話すべきことではない。独占することはできないという言葉で区切ると、これがマリーの望んでいる答えかな、と首を傾けた。
「サンソン、あなた」
立香のことを愛しているけれど、そうやってごまかしているのではなくて。その言葉は出ることはない。しかし、サンソンには伝わっているようで口を閉ざしたまま小さく頷く。
「僕は立香のことを恐らくは。ですが、いいのです。彼女は自由であるべきだ。僕が彼女自身を壊してはいけない、そう思うのです」
「そう、そう思っているのね。でも貴方、無理をしているのではなくて。だって今、私のことを処刑したときと同じような顔をしているわ」
ぐっ、と声を詰まらせる。諦めたくはない、諦められないからこそこんな事態になっているのだった。
「それにね、サンソン。貴方がどう思っていたとしても、リツカの気持ちを聞いてあげることも、しなくてはいけないことじゃないかしら。ロンヴァルの騎士様は女の子の気持ちを聞き出すのは得意ではなくて?」
継いだ彼女の言葉に、サンソンは啜りかけていた紅茶を咽させた。
「マスター、入室してもよろしいでしょうか」
『その声はサンソン?入ってきていいよ』
機械越しの怪訝な声に眉を顰めるが、その声は当然だと思い直す。マスターとは発情期の時期と戦闘時以外で言葉を交わすことがほとんどなくなっていた。部屋の開錠音と空気が抜けるような独特な音の後、部屋に入ると立香は入浴後だったようで、ショートパンツとパーカー羽織っているのみであった。
「サンソンがここに来るなんて珍しいね。何かあったのかな」
「マスター、いえリツカ。今日は折り入ってお話があり、来ました。僕が以前お話した、サーヴァントとマスターの幸せについてのお話です」
思い出したくなかったことなのか、以前サンソンがマスターのことを拒否したからだろうか、立香は大きく目を開いた。
「サンソンが、サーヴァントとマスターは幸せになれない、といったあの話でいいんだよね」
「ええ、そうです。以前僕は君を拒否して遠ざけた。けれど、今日マリーとお茶会をしたときに叱られてしまいまして。正直にならないといけない、貴女の言葉も聞かなければならない、そう思いました」
「サンソン」
「僕はリツカ、貴女のことを愛おしいと思っています。貴女のことを叶うなら番にしたいと思っている。けれど、同時にリツカには幸せになってもらいたいと思っています」
「それって、付き合うとか付き合わないとかそういう意味で好き、愛おしいってこと?」
「ええ、そうですよ。ですが、僕の気持ちを押し付けてしまうのはいけない。リツカに選んでほしいのです」
終わりの時まで番として愛をはぐくむのか、それとも今まで通りに発情期の処理として身体を求めあうのか。立香は向けていた目を一度伏せた後に顔をあげる。
「サンソン、それってずるいよ。一度私を避けて、身体だけの関係を続けて。それでもね、シャルルのこと、嫌いにはなれなかったんだよ。ずっと、好きだったんだから。ずっと私のことを見てほしかったんだから」
立香は向かい合っていたサンソンの胸に飛び込む。その耳は真っ赤で、自分の発した言葉の恥ずかしさから顔を見せられないのだとわかる。その背にそっと、今まで接触を避けていた腕をまわし、小さな体をしっかりと抱きしめる。やわらかくて仄かに感じる香りはサンソンの好みとは異なっていたが、彼女の太陽のような温かさ、甘さを感じる香りだった。
「マスター、リツカ。噛んでもよいのでしょうか」
「うん。その、サ、シャルルならいいよ。ううん、シャルルじゃなきゃ噛んでほしくない」
抱き合った後ながされるままに背を預けるとになったシーツのしわなど気にすることもなく、首に巻いていたそれもない状態で。サンソンが噛みつく場所を確かめるように一撫ですると、Ωの本能からか、それとも快楽を感じるからなのか、立香はびくりと震える。サンソンとしては立香に痛みを感じてほしくない、自分などにはとらわれてほしくないと思う反面、自分以外が彼女の番となって生きていくことなど考えたくないと思ってしまうのだった。相対するそんな気持ちに終止符をうつようにそこに鋭い歯をたてる。ベッドシーツを掴んだ手がサンソンの横でぎゅと握られ、サンソンの肩にも立香の歯がたてられる。ハジメテを奪った時には発情期ということもあり痛みを感じてはいなかったが、今はその時期ではない。痛みを素直に感じるであろう彼女に自身も同じ痛みを感じたいと申し出て肩を噛むようにしたのはサンソンであった。
サンソンの突き立てられた牙に血が滴る。魔術師の血液はそれ自体に魔力がこもる。それを摂取するために血液を通した魔力供給があるぐらいなのだ。しかし、サンソンはそれ以上の充足感と征服欲、番を得ることの興奮を享受していた。それは噛まれた立香も同じで、項の痛みによりサンソンの肩にかじりついていたが、運命の番を刻んだ体はその悦びから震えを走らせる。
傷口をなるべく広げないように気を付けながら外された項には、確かに自身に噛みついて付着しただろう痣が見えて立香は声をかける。
「しゃ、るる、……わたし、シャルルの番になれたのかな」
「ええ、発情期がこないと本当になれたかはわかりませんがおそらくは。ですが今はそれより、番もαもΩも関係なく君を抱きたい」
声には今まで我慢していた分の抑えきれない欲情の色がのっている。立香の許可が出るまでは手を出そうとはしないまでも、視線で彼女の身体の奥底に、自身と同じ灯をつけるように覗き込んできていた。立香はそんなサンソンに微笑みかけると唇を彼の耳に寄せて言葉を紡いだ。