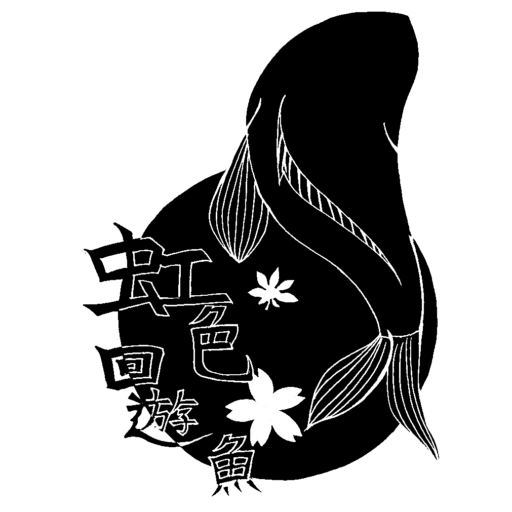藤丸立香はサーヴァント達と五つ目の特異点を駆け抜ける。人理を修復し、それを乱す元となった聖杯を手に入れた。カルデアで所有される聖杯は誰かの願いを叶えるという私欲を満たすものとしてではなく、霊基を拡張させてマスターを守る力として使われる。今回マスターの元で共に歩んできたシャルル=アンリ・サンソンは霊基再臨を行った部屋でソワソワと自分に捧げられる聖杯を、立香と共に待つことになった。
「サンソン、もしかして聖杯を渡されるの嫌だった」
「いえ、そういう訳では無いのですが、何故僕に聖杯を渡していただけるのかと気になっておりまして。僕の他にも名高く力もある英霊は沢山いますから」
「強い子に聖杯は捧げられるべきだ、と思ってるのかな。それとも自分を卑下してそう言ってるの?」
「卑下。たしかにそうかもしれません。マスターは僕を懇意にしてくださいますが、例えばアーサー王。彼のように誰もが知っているようなものであれば、リツカに負担がかかることも少なくなるのではないかと」
今は服で隠しているが、多くの戦闘で立香の体は傷ついている。勿論それだけではなく、レイシフトや模擬戦等のない日には書庫にこもることも少なくない。その結果、書庫の片隅へブランケットを持っていく英霊の姿がよく見えるほどであった。今でもサンソンには目の下に隈を作りながらも微笑んでいる立香が見えている。サンソンは隈のできた目元を小さく撫でながら『少しでもマスターに安らぎのある時間を』そう考えていた。
「起きて?こんなところで寝ていたら病気になっちゃうよ?」
「う、うん?マスター」
「ますたあ?私はりつか。ふじまるりつかだよ」
さわやかな風に反するようにじめじめとした熱気のある空気。太陽は目線の先にあることから、今は昼であることが分かったが、あたりを見渡したサンソンには全く覚えのないところであった。今まで拡張に使った聖杯は勿論、こんなことが起こったことがなく、頭をひねる。目のまえには小さなオレンジ色の髪。結ばれている黄色いシュシュには確かに見覚えのあるもので、目の前の少女は見知らぬ人間であるサンソンにこう発した。
「お兄ちゃん、もし良かったら遊ぼう?」
子供の体力は底なしだと言うけれど、自分が子供の頃、そして今の彼女とは全く異なる立香の振る舞いにサンソンは困惑した。山が近くにあるからと山登りを最初に勧められ、岩肌を登っていたと思ったら、木が生い茂る地点に着いた途端にカブトムシを探し出したり、雀蜂を網で突っついて追いかけられたりする。途中で蝉取りになって、肩車をしたらそこから落ちそうになった。川遊びをしようという話になったと思ったら、着の身着のままで川に泳ぎ出そうとするだけでなく、大きな百足ほどもある河虫を捕まえて自慢をされた。
そんなことをしている間に時間は夕方へと進んでいった。
英霊の座へと至ってから感じたことの無い疲労感を感じながらもひとつの確信をサンソンは得ていた。マスターはだんだんと記憶を取り戻している。何故こう思ったのかと問われれば、最初出会った頃よりも気を使う素振りを見せられたり、いつものような、悪く言ってしまえばどこか疲れたような何かを知っているような瞳を覗かせていたりしたからである。現に今でも普段と変わらない、まとわりつかない程度の程よい距離感を保っていた。サンソンは立香に声をかける。
「マスター、そろそろ戻りましょう」
もうご自分のことを思い出しているんですよね。問うサンソンの顔は確信を得ているようで、誤魔化しもきかないだろうと立香は口を開く。
「多分このまま手を繋いで歩いていけば戻れるとは思うんだけれど、よく気がついたね」
「ええ、マスターのこと、いえ、リツカのことですから、すぐに気がつきましたよ。記憶が戻っていると。少しずつでしたが、戻っていらしていたのでしょう」
「うん。最初はサンソンが肩車した私が落ちかけたのを助けてくれた時だったかな。この感覚、感じたことがあるって」
「あれは驚いただけではなく、背筋が凍るものがありましたよ」
「うん、ごめんね。でもそこから全部を思い出したんだよ。崖から落ちかけたとき時助けてもらったこと、焚き火の周りで食事をとっていた夜、その他にも君と共有した夢だって。」
立香はサンソンを見上げる。彼は今までを懐かしむように一つ一つの言葉にうなずく。
「それで全部思い出して、どうしてこんなことになったんだろうって考えていて、思ったの。今回のこれは、サンソンが原因じゃないかって」
「僕、ですか」
「うん。だって私は何もしていないし、聖杯に願ったことなんて何一つないもの。でも、サンソンは、聖杯に接触する前に何か考えていたでしょう。」
「ええ、たしかに考えていました。その、少々烏滸がましい話になってしまうかもしれませんが、マスターは最近休まれることが少ないでしょう」
「う、うん」
「睡眠時間を削って本を読まれて。僕達のことを理解していただけるのは嬉しいですが、マスターにはもっと休息と安らぎの時間が必要かと」
「無意識に聖杯にそれを願ってしまったかもしれない、ってこと」
「ええ、もしかしたらそれでこの世界、夢にこの一日に閉じ込められてしまったのかもしれません」
「それって完全に私のせいだよね。ごめん。でも、ありがとう。私の一番楽しかった時間に君と過ごせて、すごく癒されたよ」
小さく笑って離れていた手に手を合わせる。サンソンは何か言いたげな顔をしていたが、手は逃げずに、立香の手をぎゅっと握った。
「おはよう。立香くん、それからサンソンくんも」
「呼吸も意識レベルも安定していますね。それから……光をあてた時の瞳の動きも問題ない。間違いなく正常です。おかえりなさい、マスター。あなたの中の病魔は完全になくなりました」
「あ、ありがとう。ナイチンゲール」
目が覚めた瞬間に、「治療を開始します」と声を上げたナイチンゲールと、慌ててそれを止めに入ったダヴィンチに、随分心配をかけてしまったんだなと思いながらサンソンと医務室を出る。他のサーヴァントに会ってしまうと、また慌ただしくなることは理解出来ていたので、なるべく二人で気配を伺いながら人気のない場所を選んで進み、部屋に着く。マスターの回復はあとで館内放送でもしてもらえればいいだろうと話し合ったあと、そのままサンソンと別れようとするが、声をかけられた。
「マスター、少々お伺いしても」
「何。どうしたのかな」
あの夢を共有してしまったことで今更隠すことなんてないだろうと思い、何でも聞いていいよと答えると、サンソンはそれでも迷いが残っているかのように、何度か口を閉じたり、開けたりを繰り返す。
「その、マスター。僕の聞き違いでなければですが、あの時、一番楽しかった時間と、口にされていましたよね。」
「ああ、うん。その事。サンソンは気になるよね」
「ええ。申し訳ないとは思いましたが、あの時のあなたの顔が、あまりにも、寂しそうな顔をしていたので。僕が聞いていいことかはわかりませんが」
なんだその事か、と何度も人に話していたことだったので、笑顔を浮かべて話し出す。仲が悪かった両親のこと。たった一人の兄のこと。ある夏休みに私だけが祖父の家に預けられたこと。その間に両親が離婚して、兄が父親の元に、母が私を引き取ったこと。それからは平日も特別な日も誰かと一緒にいたことは無かったこと。誰もが片親の私を、まるで腫れ物でも扱うかのように関わろうとしなかったこと。
なるべく自分の中の感情を動かさないように話を進めると、サンソンは次第に眉を寄せていく。
「と、こんなことがあったから、一番楽しかった時間って言っていたんだけれど」
「マスター、それは」
「下手な同情とか、そういうのはいらないよ」
私は欲していないから。立香は否定をする。重すぎる話なのだ。ひとりでかかえきれなくなるほど重いものであるが、それを無理して笑っているのだ。完全にわかる訳では無いだろうが、サンソンにはどこか覚えがある無理のある顔であった。サンソンは救いになる声をあげる。
「マスター。下手な同情等ではありません。あなたの辛かったこと、楽しかったこと。すべて話していただけませんか」