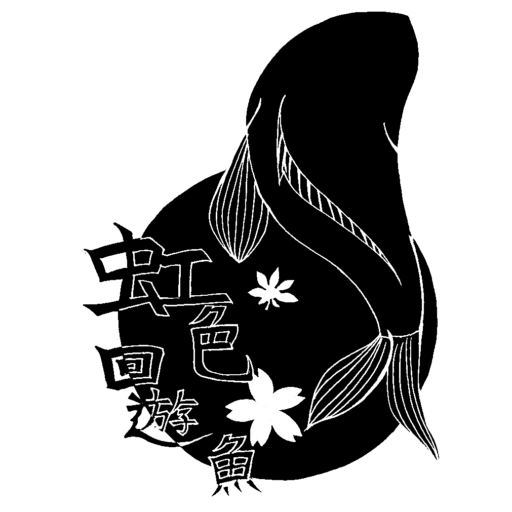自分はマスターに嫌われている、または避けられていると感じたのは自身の影とも呼べる狂化がかかったバーサクアサシンに出会ってからだったと記憶している。マスター自身の部屋に呼ばれ、有事の際の警護をしていることもあったが最近は呼ばれることもなく、マシュが常にマスターと部屋を共にしている状態であった。
確かに僕は誰もが苦痛を感じない処刑を望んだ。それに王妃への敬愛の感情はあれど、僕自身は断じてあそこまで狂ってはいないのだ。それを自身は理解しているが、マスターには同じ見た目を持っている、同じ要素を持つものとして映ってしまうのは当然のこと。第一特異点であるオルレアン、聖杯取得後のその土地でライダークラスのワイバーンの活動が活発になったと聞き、アサシンクラスである僕を含めたパーティーでエネミー退治を行っている今もそれは変わることはない。
辺りを見渡し、一匹も敵の影が見えなくなったことを確認した後に、サーヴァントの傷の回復を行う。マスター自身の持てる魔術での治療も加わり、あとはマスターの回復となったところで、休憩地点にしていた近くの、崖のようになっている場所からふわりと風が舞い、叫び声とも咆哮ともとれない音が響く。
「サンソンさん、残党。ワイバーンです!」
「マシュ、わかっている。マスターを早く安全なところ、へ」
会話途中にもワイバーンが放った一撃で、マシュを含めた何人かのサーヴァントが地面ごと吹き飛び、そのままはるか下へと落下する。どうやら休憩していたところ自体が一枚の薄い板のようになり、まるで台地であると錯覚するように広がっていたことに、今更ながら気が付いた。幸い自身と、後ろにとっさに庇ったマスターがいた部分は下に岩があることで支えられていたためか、何事もなく立っていられる状況であった。
「アサシン、ごめん。大丈夫?」
「ええ。私はサーヴァントですよ、マスター。私のことを思うのであれば、令呪の発動……そして宝具の使用を命じてください」
「わかった」
彼女は偶然に仕えるべき主になっただけである。個人的な情などかけるべきでもないだろうと判断して、なるべく感情がこもらないように答えた。それに対して、どこかおびえた目で答えるも、自身のやるべきことを理解しているのであろう、右手を掲げて意識を集中。僕と魔術回路をつなげていく。
「マスター、もう十分です。あとは下がっていてください」
「アサシン、宝具の発動を」
刑を執行する。返事の代わりにとワイバーンの背後に出現するギロチン。あとは黒き手が相手の体を拘束し、刃が下ろされるのを待つだけだ。最後まで息を抜くことはしないが、彼らが翼竜を拘束するのを見届けるために小さく息を吐く。
一つが首の根元をつかみ、さらに一つが羽の元に絡みついていく。動きを制御されるのが気に入らないのか、それはほとんど巻き付かれた状態でも暴れだした。大きくうなると黒い帯のようになったそれに噛みつき、再び空へと舞おうと試みる。勿論それは阻まれ、決して傷を負うほどではないが、狂った空気の渦が圧となって直撃する。
「うっ、ぐ。La Mort Espoir.」
死は明日への希望なり。声を張り上げたと同時に無慈悲に降ろされる死の刃。その刃の前には身分も、性別も、生まれも、何もかもが関係ない。ただ、罪とされるものと分かつ。ワイバーンの首にそれが触れ、血飛沫がわずかにあふれ出すそれを見ながら、これでよかったのだと胸の内に留めた。
私が召喚したサーヴァントたちは、どうしようもなく非力な私に力を貸してくれる。勿論目の前で巨大な翼竜と対峙している黒いコートの処刑人もその一人であるのだけれど。
私が彼と出会ったのはこの地、オルレアンへとレイシフトする少し前のことであった。カルデアが壊滅的な被害を受け、私を先輩と慕ってくれるマシュもがれきに埋まって致命傷を受けた。何とか帰還し、召喚できる部屋をカルデア内に整えた。そこで初めて来てくれたのが彼であった。歴史に詳しいわけではなかった私に対して、彼は自身を処刑人であると話した後に、
「私のことは真名ではなく、そうですね、アサシンとでもお呼びください。それから、私は貴方の刃でありますが、同時に貴方を量る天秤でもあります。そこをお忘れなきよう、お願いします。」
と、差し出した手をよけるようにして、困惑した表情を向けられる。人類最後のマスターとして、人として正しい道を歩む限りは、常にサーヴァントとして従う。そのことを続けて言う彼に、自身がマスターでなければならないと、彼にとっても、その他の仲良くしようとしてくれているサーヴァントに対しても、マスターでなければならないということを大きく自覚させられた。
それからオルレアンの狂化がかけられた彼に出会い、今日まではマスターとサーヴァントとして一線を引いている。狂化をかけられていた彼と同じ容姿の彼に恐怖を抱くことがあれども、マスターとサーヴァントとしては十分な関係を築けているのだろうと思っている。
「マスター、もう十分です。あとは下がっていてください」
「アサシン、宝具の発動を」
真名で呼ぶことができないのは少し悲しいかな、そう思いながらも彼の指示通りに後ろへ半歩ずれる。あまり下がりすぎると、先ほどの風によって砕かれて崖となった場所まで落ちてしまうから気を付けた。マシュたちは無事なようで、下から安否を確認する声が上がっているが、彼の宝具を発動すればおのずと無事であることは分かるだろうと再び前を向く。彼の宝具であるギロチンの刃が落ちると同時に発せられる「La Mort Espoir.」という声。同時に全身に当たる姿の見ええない圧力。あっ、という間もなく翼竜の風に吹き飛ばされ、崖下へと落ちていった。
「きゃっ」
こんなにかわいらしい女の子な悲鳴を出したのはいつぶりだろうな、小学生の頃にクラスの男の期にスカート捲りをされて起こった時だっただろうか、そんなどうでもよいことが浮かぶのが、走馬燈。重力に逆らうかのように、もしかしたら足を滑らせた崖に手が届くかもしれない、そう思って手を伸ばす。勿論それは届くことはなく、落下していくが、途中でゆっくりと落ちていく時間が現実のものへと戻った。
落下場所に下のサーヴァントたちは間に合わないだろうし、落ちる衝撃からは身を守れないだろう。無意識に閉じていた目を開けると、未だに全身に感じる重力と、手首での位置で引き延ばされた布。それを掴んでいるのは当然先ほどまで目の前にいたアサシン、シャルル=アンリ・サンソン。そのままどこか遠くを見ているような状態の彼に引き上げられ、抱きしめられる。
「今度は、間に合った」
「アサシン。く、苦しいよ」
シャルル=アンリ・サンソンには二人の息子がいた。一人はシャルル=アンリの後を継いで処刑人となったが、もう一人、ガブリエルは絞首台から落下。そのまま命を落とした。
作家サーヴァントの一人がどこか悲劇の物語を語る様に腕を広げて語っていたのを思い出す。サンソンを召喚して、彼のことを少しでも知っておいた方がいいだろうと思い、カルデア内の書庫にこもった時に彼に関する本と共に教えてもらったのだった。
彼がもし本当に息子を亡くしていたなら、彼の苦しみを呼び起こすこととなってしまっていて。彼が言っていたようにただ彼のことを使役するだけのマスターであっていていいのか、彼はシャルル=アンリ・サンソンという私と同じ一人の人格を持つものであるのではないか、と思いが膨らむ。その思いに従って、いまだに私の声が聞こえていないのか抱きしめ続けるその体に腕をまわす。そしてそっと、背をなだめるように撫で上げた。
「マスター」
「アサシン、ううん、サンソン。それとも、シャルルの方がいいかな。とにかく、サンソン。私は、私は死なないよ」
「ええ、わかっています。あなたは死んでいません。ですが」
「うん、わかってる。さっきはもしかしたら油断していたのかもしれないし、マスターとしては緊張感がなくて、失格だよね」
「いえ、そういうわけではないですよ。僕は、僕こそ、サーヴァントとして、貴女と共に戦っていくものとして、間違えたことをしている自覚があります。あなたはマスターであると同時に、一人の人間であり、リツカという生きているものだ。マスターという鎖に縛りつけてはいけなかったのです」
自分というものは使役されるだけでも一向にかまわないが、マスターをマスターとして縛ることは間違えている。そう続ける彼の口を手で塞ぐ。
「サンソン、それ以上はマスターである私が令呪を持って命令してでも言っちゃいけないって止めるよ」
だって、サンソンはサンソンであって、私と同じく人格を持っていて、性格もとてもまじめで、誠実で、頼りがいのある人で。確かにあの時に出会った君のコピーともいえる彼は怖かったけれど、君は、シャルル=アンリ・サンソンは私にとってとても大切な人たちの一人であって。続けようとすると、肩を掴まれてそのまま距離を置かれる。
「マスター。僕は最初にお話ししたように、ただの処刑人です。自分で自分のことは理解しています。僕自身はマスターの思っているような人物じゃない。ですが僕は、貴女が、フジマルリツカが望むなら、マスターだからではない、貴女のために刃となりましょう」
跪き、誓いを立てるように彼は話した。
「サンソンさん、召喚されたころと比べて先輩と打ち解けているようで安心しました。」
「えへへ、ごめんねマシュ。心配させていたかな」
「心配は、していましたね。先輩もサンソンさんもどこか無理をしていたような、無理やり型にはまった関係を築こうとしていた気がしましたけれど、最近は自然体として話しているようで。とにかく、良かったと思いました」
オルレアンから帰ってきてから。私はサンソンに最初に頼まれていたことを反故にして、彼のことをアサシンからサンソンへと呼び方を変えた。そうすることが、彼を彼として見ていることになると思ったからで。彼もそれに合わせたのか、思うところがあったのか、私のことをマスターという呼び方だけではなく、リツカと呼んでくれることも増えてきていた。
ただ、まだ信頼が築けていないのか「首を刎ね、血に染まった手。そんなものに触れて何になると」そう自虐的に聞かれたり、私が偶然にも彼に接触しそうになった瞬間に彼から避けられることもある。それでも、私は彼のことを知って、少しでも彼と打ち解けていければ、と強く思った。