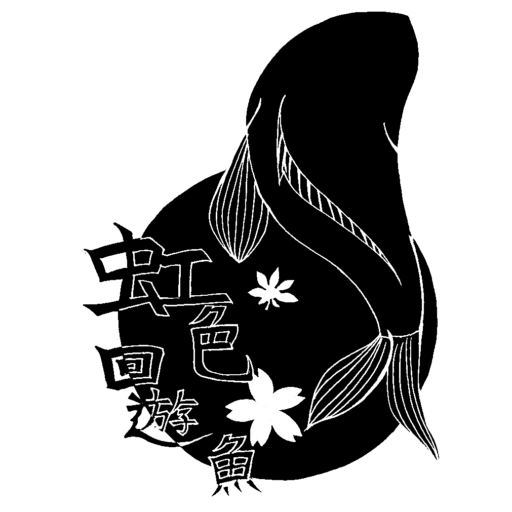告白
いつから彼のことを好きになったのだろうと考える。気が付いたのは、彼が絞首台で風に揺られているのを見た時だった見たときだったのだろう。いつも隣に立っていた彼がもう返事をすることはなく、ただ風に揺られていた。令呪を使うことを許されずに、ただ段を上って首にそれをかけられて、足元が落ちる。その瞬間を見ていることしかできずに、マスターとして以上に感じてはいけないと思っていた感情があふれ出ていたのだった。
シャルル=アンリ・サンソンという概念として再召喚することはもちろんできるが、もう一度出会うことがあったとしてもそれは私が今まで一緒に過ごしていた彼ではなく、彼と同じ姿を持った別人だったのだろうということは理解していた。
「そこで気が付いたから、最近様子がおかしかったんですね」
「うん。というか、ごめんね。こんな話しちゃって。こういう話聞くのって気まずいでしょ」
カルデア内の食堂。全員に声が筒抜けになるだろうけれど、逆に誰も人の話なんか盗み聞きすることはない。そう思って、少しずつ話し始めたことが続いて三十分。目の前にあった、温かい炊き立てご飯とお芋の煮っころがしはとっくに冷たくなっていた。
「まあ、確かに気まずいといえば気まずい。けど、どこかぎくしゃくして、トラブルでもあったのかと思いきや、まさかアンタが恋愛で悩んでいるなんて。少しは余裕が出てきたってことで、俺としては安心しましたよっと」
セイレムの後からサンソンとうまく付き合うことができなくなっていた私に、自分があの時止めたせいもあって関係が悪くなっているんじゃないかと考えていたロビンが、食事ついでにと声をかけてくれたのだった。その彼はというと、とっくに食べ終わっているお皿を横に片づけている。
「ロビン、その、ありがとう」
「ん。まあ、話して少し楽になったらよかったんですけどね。それで、俺は協力した方がいいですか。あのセンセイがどんなのが好みかは分からないですけど、同じ男としてわかることもありますぜ」
「あはは、それはいいや。でも、もし私がこのままうまく話せなかったりしたらマスターとして駄目だから、そのときには叱ってほしいな」
これは自分の問題だからと思わず苦笑しつつ、二人で立ち上がる。結局冷たくなってしまった食事は自分の部屋で食べることにして、ロビンはロビンでビリーくんたちとの賭け事のためにと、お互いの場所へ向かった。
それから三日後。サンソンと会話を試みようとするけれど、どこかつっかえてしまってぎくしゃくする状態が続いていた。
「先輩、最近サンソンさんと何かありました?」
夜の入浴を済ませた後にベッドに寝転がっていた私に、警護を申し出てくれていたマシュが声をかけてくる。
一応人類最後のマスターの私は、サーヴァントの一人を選んで部屋に招き、毎日警護をしてもらっている。大体が今のマシュのように同性のサーヴァントに直接お願いして警護してもらっているのだけれど。
「やっぱり気が付いちゃうよね。マスターとサーヴァントとしては何もないけどね。その、えっと」
女の子同士だから別に気にすることはないと思うけれど、私のことを慕ってくれているマシュにこの気持ちのことを口にするのは何処かはばかられてしまう。それでも、なんとかも小さな声で話し始めた。
「先輩。先輩は一度サンソンさんとお話しすべきです。私が先輩の立場なら、何もしないでお別れよりは話したいと思います。それに、私でしたら警護から外れても大丈夫ですよ」
「え、ええ、でも」
一件を話し終えるとマシュは、さあ、ほら!と、変なスイッチでも入ってしまったように、私を呼び出しの画面に向かわせる。私はその勢いにいつの間にか正座になっていて、そのまま片手を伸ばして端末を起動し、少し前から使っていなかった番号を押していった。
『はい、マスター』
機械越しの小さな声。努めて声が震えないように声を絞り出す。
「さ、サンソン、こんな夜遅くにごめんね。その、今日の警護のことなんだけど」
『今夜はマシュに任せると話していましたよね。それを変更したいということでしょうか』
「うん。マシュにはお願いしたんだけど、もしよかったら今から来てもらえないかなって思ってて」
『ええ。わかりました。では、少し準備を整えてから出ますので、お待ちいただいても』
「うん。勿論だよ。こんな急に呼び出してごめんね」
『いえ。ではまた後程』
通信が切れると同時に、体の力が全部抜けたようにうつぶせになる。
「先輩、しっかりお話してくださいね」
と、マシュが隣に座って頭を撫でてくれて数分。入室の許可を求める声にマシュが出て、何か一言二言話したあと、入れ違いになるように彼が入ってくる。対して私はいまだにうつぶせになっていたから、ベッド端に座り直して、サンソンに隣に座るように促す。
「えっと、サンソン。その、えーっと」
実際に彼がすぐ横に座っていると意識してしまうと、どうしてもつかえてしまうようで、言葉が出てこない。それよりも、何を話そうとしていたのかと、頭が混乱してくる。
「マスター。僕は以前『地獄の底まで、天の果てまでつきあいましょう』と言ったことがありますよね。僕は、あなたと共に人理修復をしてきて、あなたと共に歩んでこれるのがうれしいと感じていました」
「うん。勿論私も。こういうのは変だけど、最後まで君と一緒にいることができてよかったなって思うよ」
「ありがとうございます。話の続きになってしまうけれど、僕はあのセイレムで君に教えてもらったこと以外で、何かしてしまったのかな」
セイレムで起きたことについての概要はすでに彼に話していた。セイレムの後から私に態度の変化に彼も気がついていたのだと、ため息をつきたくなる気持ちを押し込めて息を吸い、彼を見上げる。
「ううん、違うの。それって私があの後から距離をおこうとしたり、変な態度をとっちゃったから、そうやって聞くんだよね」
マスターとしてしっかりとしなければいけないのはわかっていたけれど、セイレムを通して、君がいなくなってしまったのが悲しくて、絞首台から延びた紐につられているそれを見た瞬間に、今いる君がもう戻ってこないと気がついてしまったんだ。そう話を続ける。
「それで、君がいなくなって初めて、マスターとしてじゃなく、藤丸立香としての気持ちに気がついたの。私は、君が、シャルルが好きだったんだって」
目の前の彼と、あのときの彼が重なり、もう泣くまいと決めていたのに涙が溢れる。
「マスター。いえ、リツカ。泣かないでください。僕も愛おしいと思っている貴方に泣かれるのは心が痛みます。今月の二十六日には僕たちの退去が決まっていることはすでにご存じでしょう。だから、僕は貴方にこの気持ちを伝えるつもりはありませんでした」
僕もリツカのことを愛おしいと、好いているのです。流れたそれを拭われ、頬に口づけを受ける。
「それを抜いたとしても、僕とリツカはサーヴァントとマスター。特にリツカはたくさんの契約をしている身であって、僕としては負担をかけたくないと思っていた。けれど、リツカが求めてくれたなら、僕としても君を近い最後の日まで求め続けたいと思う。リツカは、すぐに別れることになるだろう僕と、付き合ってくれますか」
「うん。シャルルこそ、私なんかでいいの?」
恋人としての一番はシャルルでも、私の存在は沢山のサーヴァントに必要とされている現状、その点においては一番として扱うことができない。
「勿論ですよ、リツカ」
そう言った彼は優しく微笑みかけてくれた。