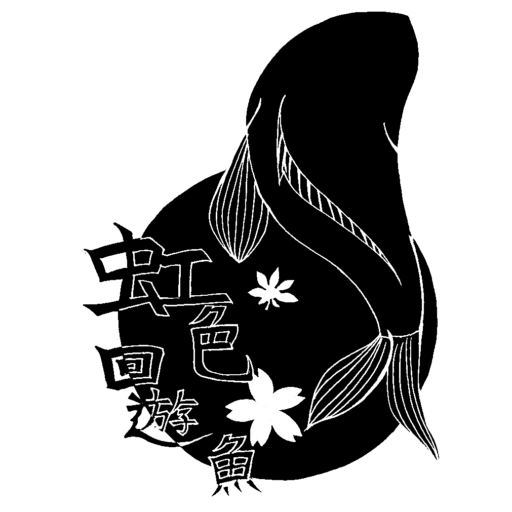追想の愛(R-18)
彼が食堂から持ってきてくれた食事は冷めないうちに食べられる。合間に喉が渇いたと飲み物を探せばお酒の代わりに出されるキンダープンシュ。立香の目の前で飲んでいるサンソンのそれは同じようなものをだけれど、香りからお酒であろうと予想が付いて、つい好奇心から飲んでみたいといってしまっていた。
「リツカの出身国においては二十歳になったら飲えるようになるものではなかったでしょうか?」
「うん、そうだけど目の前でおいしそうに飲んでると気になるんだよね」
「ではリツカも飲んでみますか」
もちろんそのまま飲むのは僕も見過ごせませんが。唇の端に薄く残ったそれを彼らしくない動作、舌で舐めとる。その表情には肉体年齢に合わないアンバランスな色気があって、思わずごくりと口に含んだキンダープンシュを飲みこんだ。
「っ、ぁ」
「はぁ……リツカ。そんな顔をしないでください」
食後にベッドの淵でサンソンからの激しいキスの後を受けた後、揺らぐ視界をそのままに彼を見つめる。付き合ってから手をつなぐことも、抱きしめ合うことも、軽いキスから激しいものもしたけれど、それより先に進んだことはなかった。生真面目な彼のことだから簡単に手を出してはいけないと思っているのではないか。そう立香は思って彼に先にすすんでもいいという意味を込めた視線を送ったのだ。
「シャルル、なんで。私、もう……その、いいよ」
「ダメです。ダメだ。マスター、その声と顔で僕のことを呼ばないでください」
確かに僕はリツカ、君のことを愛しています。だからこそこうやって関係を深めてきました。それに後悔はありません。ですがこれ以上はだめです。僕はサーヴァントであって貴方は僕のマスターだ。僕が未来を恐れることはありません。今一時に仮初めの肉体を持ち生きている、未来がないものだからです。無くなるとわかり切っているものに対して恐れる必要はない。けれどリツカは違う。未来があり、そこで生きていかなければならない人間です。未来を共に生きることのできない僕にそうやって、君自身を簡単にささげてはいけない。
そう言って眉をゆがめた後、たまらないといったように首に唇を押し付け、抱きしめる。立香はサンソンの背に腕をまわそうとし、拒否されることがなかったのでそのまま優しく抱きしめて、背を撫でる。
「サンソン。ねえ、シャルル。私、シャルルがそこまで考えてくれているのは嬉しかったよ」
「ええ。僕の気持ちを理解していただけましたか」
「うん。でも、それでもね、私はシャルルの気持ちを無駄にしちゃうかもしれないけれど、シャルルに抱いてほしい」
「……マスター」
「シャルルは私のことを大切だと思っている。それに君が還ってしまった後のことも考えてくれているんだよね。でも私は、君に抱かれなかったら、きっと後悔すると思う」
「マスター、それは」
「それは私の気持ちだよ。シャルルの考えたもしもの話じゃなくて私の気持ち。シャルルに抱かれなかったら、きっと付き合っていたことも、何もかも、思い出したくないものになっちゃうよ。だから、シャルルに愛されたってことを私に刻んで。後悔するような記憶にさせないで」
そっとサンソンの耳にささやかれる言葉。それは彼の中の獣を起こす暖かな音色のよう。サンソンは首筋にもう一度噛みつくようにキスをする。
「リツカ、君は僕の望んでいる言葉をくれるのですね。僕としては警告の意味も込めていましたが、リツカが望むなら、後悔しないのであれば僕としても、うれしいです」
これは最後の警告です、今ならまだなかったことにできます。そう言いながら首筋、そっと緩められたシャツから覗く鎖骨に口づける。ベルトも慣れているとは言えない手つきだが、リツカ自身が外すよりは器用に外してそのままシャツもスカートも取り去り、サンソン自身も肌を晒す。
「リツカ、これは?」
立香の肌にはこれまで駆け抜けてきた特異点で受けた傷がいくつもついているのは、サンソンも治療に当たることもあったので知っていることだ。その傷さえも、生きていることを証明しているようで美しいと感じていたのだが、今彼が驚いているのはそういうことではない。カルデアではマスター含め職員は指定された衣服を着ている。それは見えるところだけではなく、下着も含めて。けれども今マスターが着ていたそれは物資が少なかった中で混ざるはずもないもの。白を基調とした繊細なレースを施されたそれは、足のちょうど付け根にあたる部分だけが色を変えていた。
「うう、ここに来た時に持ってきていた荷物の中に入れてたやつだけれど、変だったかな?」
「いえ、変では。ただ、支給されているものを身に着けているかと思ったので」
「だ、だって、もしかしたらシャルルと、えっちなこと、するかもしれないって思ったから」
「僕のために選んでくれたんですね。すぐ脱がせてしまうのももったいない」
そう思案しながらも立香の足の間に体を割り込ませて足を閉じないようにする。濡れたそこのすぐには手を伸ばさない。勿論立香が快楽を簡単に得られるだろうそこを刺激することも一瞬考えたが、サンソンは一番後にお気に入りを取っておく人物だ。それに最初に強い刺激を与えるより、じわじわと指先から快楽を与えるように全身を快楽に染め上げてからの方が自身も強い快楽を得られることを経験で知っていた。
過去に関係を持った女性と一緒にする気は一切ないが、立香は初めてなのだ。初めてで絶頂させることができるだろうかと不安にはなるが、少なくても苦痛よりも快楽に浸ってほしい。
口づけで気をそらしながらも背中に手をまわし、立香のブラジャーを浮かせる。そのまま紐を彼女の腕から抜くと、感嘆の溜息を思わず漏らす。布を一枚取り払っただけだが彼女が着やせしていることがわかる双丘。手を頂には届かないよう、触れるか触れないかの距離で撫でつけるように手で触れる。そうして何度も触れていくたびに、立香は小さく声を漏らす。
「ぁっ……!やっ、まって、シャルル。んぅ……」
「リツカ、こうするとよくはありませんか。ここを触られるのが嫌でしたら、こちらはどうでしょう」
「んっ、ぁ……っぱいの先は、だ、めぇ」
サンソンが一方を爪で軽くひっかくように荒くし、固く立ち上がるまで手でなでつけたもう片方に口を落とす。舌先で舐める。気まぐれに吸い上げるようにしたり、口を離して冷たい息を吹きかける。立香はそれがたまらないというように、一つ一つの行動に声を漏らして、これ以上はやめてほしいとも、続けてほしいともとれるようにサンソンの頭を抱きしめる。
「リツカ。離してくれませんか。これだと君にベーゼできない」
「ぁ……はぁ、ご、ごめん、ね。その……ぞくぞくして、つい」
「リツカ、そのぞくぞくしているのが気持ちがいいということですよ。」
「きもち、い」
「ええ、そうです。僕が少し触るだけでこんなにかわいらしい反応をしてくれて、嬉しいです。リツカ、気持ちいいって言ってくれませんか。それから声も我慢しているよですが、僕としては出してくれた方がうれしいです」
「う、ん。恥ずかしいけど、シャルルが言って欲しいなら」
ありがとうございます、と目元、唇、首筋、下へ向かうように口づけを落としていく。そのまま先ほどと同じように胸の頂を口に含むと、ふるふると震える立香。心なしかサンソンの腰を足で挟むように、こすり合わせるようにしているのを感じながらもそのままに、喘ぎ声と、きもちいい、と約束通りに口にする立香に直接的な快楽を感じはしないものの、恥ずかしがっている様子に加虐心、そして肉体を支配していることに征服欲が満たされる。そして胸を触る手をそのままに足を折り曲げて器用に立香の付け根に押し付けるように動かす。
「あああ!あっ、しゃ……!ぁああ!そこ、ゃ……き、きもち、いい」
「ここ、ですか?触ってもいないのに僕の膝を濡らしてしまうぐらいぐちゃぐちゃになってますね」
ぐりぐりと、痛がらない程度、快楽を享受できる程度にいじめる。けれどそれだけでは足りないのだろう。立香の目に涙の薄い膜ができる。
「シャ、ルル。足じゃぁ、や、……だ。も……ぐちゃぐっ、ちゃだし、きて……?」
「はっ、……リツカ、だめです。まだ慣らしてもいない。リツカの中にこれが入るんですよ」
手を取り、立香が拒否しないのを確認してからボクサーパンツ越しにその熱に触れさせる。日本人のそれと、サンソンのそれは大きくサイズが異なることを理解していた。性行為を行うのはそのものの近しいものが一般的なことで、そのサイズを受け入れることができるようにはなっている。勿論何度も行為を行えば体がなじむことによって受け入れることができることも知ってはいたが。つまり立香のそこに対してサンソンの一物は規格外なサイズということだ。
「んっ……ぁリツカ?」
立香の反応が全くなかったことで、思案に暮れていたサンソンが感じる突然の直接的な快楽。立香が顔を赤くしながらそこを確かめるように手で触り始めていたのだった。サンソンも立香に触れながら興奮もしていたことからすぐにくちゅくちゅという音が先から聞こえ始める。ボクサーパンツを脱がせて直に触ると、声は抑えているけれど手を動かすたびに足をわずかに痙攣させる。立香は自分と同じように快楽を得ているのだろうということがわかったのか、嬉しそうに表情を緩める。
「は、ぁ……リツカ。気持ちいいけど、やめて、ください。我慢できなくなって、君を傷つけてしまいますから」
手を再び掴んで、立香の顔の横に縫い留めるようにした後に離す。そのまま体のラインをなぞる様に下がっていき、ショーツの淵に手をかけて脱がす。脱がした後に残ったあたたかな銀糸に誘われるように、敏感で立香が触ってほしいと思っていた部分へと手を這わした。親指の腹で、媚肉をかき分けた先にあるクリトリスを刺激しながら、人差指を埋めていく。初めてならば狭くて指さえ受け入れるのが困難なのでは、とサンソンとが考えていたこととは裏腹に、そこはぐちゃぐちゃにとけきっていて、2本目までは入りきる。3本目はさすがに入らないと拒まれてしまったが、クリトリスを刺激しながら指を出し入れすると、ぎゅうぎゅうと締め付けられる。そのようなことなからも立香が快楽を得ていることがわかった。
「ぁ、ぅ……しゃるる、しゃるる」
「リツカ、気持ちいいですか。そう。君はうなずいてくれるんだね。初めてなのにこんなにも受け入れてくれるなんて本当にうれしいです」
「しゃるる、もう、ぁあ、だい、じょぶ……だから、ちょうだい」
「あぁもう、わかりました。本当に僕なんかでいいんですね、とは言いません。リツカ、難しいだろうけれど、ゆっくり呼吸をして。それから痛かったら僕の背中に爪を立ててください」
サンソンは立香の腕を背に回すと、足を広げさせて蕩ける場所に自身の肉棒を何度か擦り付けて蜜をまぶす。十分にそれが広がって抵抗がなくなってきたと感じると、そのまま亀頭を入口へと埋めていく。
「ぅい……ぁ、あ」
わずかな抵抗感を感じた瞬間、ぎゅっと立香の腕に力が込められてサンソンの背に爪がたてられる。痛みはあったが、それは立香が感じている痛みよりずっと軽いものだろう。一番太い部分がはいり、それから少しして亀頭に最奥が当たる感覚を感じる。立香は声を上げないようにと噛みしめないようにはしていたけれど、大丈夫だろうか。サンソンが乱れた彼女の髪の毛を払うと、彼女の眼には生理的なものかそれとも別のものか、涙が浮かんでいる。
「……しゃるる、も、……ぜんぶ?」
「ええ、挿りましたよ。すいません、リツカ。君を泣かせて、痛い思いをさせてしまって。僕の医術を使って痛みを少なくすることもできますが」
「ううん、いいの」
サンソンの言葉の途中で重ねるように立香は言葉を紡ぐ。
「あのね、痛くて泣いてるんじゃないんだよ。わたしは、シャルルとつながれて、うれしくて」
「リツカ」
眉をよせると、あふれ出た涙に口づけを落とす。何度も、何度も、立香の感じる膣内の痛みがなくなるまで、立香のうれし涙が止まるまでそれは続く。
「シャルル、あの……もう、大丈夫だから……ごめんね、驚かせちゃって。つづき、しよ。」
眼の縁を赤くしたまま首をかしげておねだりをする立香にサンソンは胸を打たれるとともに、下半身に再び熱が集まる。いいのですね、と確認をとられた後、立香は腰を押さえつけられて、遠慮がちに打ち付けられる。挿れた時から性感を少しずつ感じていたのか、それとも時間をかけたことで慣れたのか、痛みをそれほど感じていなかった。それどころか。
「あっ、ぁあ、ああん、ん!」
「リツカ、はっ、はぁ……」
「ぁ、や、やだ、シャルル。きもちいいけど、怖い」
奥を突くたびにさらに奥へ引き込もうと、入り口まで戻るたびに出ていかないでほしいと切なそうに絡みつくそこに喉を鳴らしそうになるサンソン。彼は立香の『怖い』という言葉に一つの可能性を思い起こし、腰をより強めに打ち付ける。
「あ!ああっ、ん!ひぁ!……しゃるる、やだ!ぁ、あぁ!」
「きもちいいんですよね、それで、どこかにいってしまいそうになる。そうじゃないですか?」
「そう、なの。気持ちよくて、なにも……かんがえ、られなくて!あっ」
「それに、まかせて……ください。ぼくも、あなたの膣内で……!」
「……っ、ひぁぁあああ!」
サンソンが立香に声をかけた瞬間に、我慢できないというかのようにきつく締めつけながら快楽の頂点へと向かう。サンソンはその締め付けに耐えられずに己の精を吐き出した。
「やあ、よく来てくれたね」
「ええ、まあ。貴方に呼ばれたのならば行くしかないでしょう」
絶頂を迎えた疲れからか、そのまま眠ってしまった立香の体を清めて、服を着せた。全体を整えてから部屋を出ると、ダヴィンチ女史からの手紙が落ちていたのだった。
「立香くんと、お別れはできたかな」
「ええ。マシュだけではなく、貴方のご協力も、感謝いたします」
「そんなに形式ばったことを言わないでくれたまえ。立香くんだって一人の女の子だ。君と少しの時間でいいから過ごしたかったんだろう。私としては、こんなことに巻き込んでしまった彼女への罪滅ぼしの一つなのさ」
「やはり、明日。いえ、もう今日の時刻ですね。今日中に退去しなければいけないのでしょうか」
「うん、残念なことにね。それで君は、もう座に還ることにしたんだね」
「はい。……もうお別れはすませてきましたから。僕には後悔も何もありません。ただ、彼女がこれからを幸せに過ごしてくれればそれでいい」
仄かに笑みの乗った顔でサンソンはそう答える。きっと本当にお別れを済ませてきたのだろう。彼に後悔はない、それならばもしかしたらこの話は彼にとって酷なことになるのかもしれないと思って手元にある鞄を足元の、彼に見えない場所にしまい込む。
「そうか……それだったら、またもし『マスター』に呼ばれることになったら」
「その時は、『マスター』と最後まで生き残るために戦いましょう」
「うん、その調子こそ君だね、サンソン君」
彼はダヴィンチの部屋から退出した。
十二月二十六日 退去日
立香が目を覚ました部屋は一人きりで、最初から誰もいなかったのではないかと錯覚するほどのものであった。
けれど、立香は下腹部に痛みを感じたし、目が覚めて一番の場所には彼がいたであろう痕跡。植物の紫苑が置かれていた。
「わたしもきみのことを、ね。シャルル」