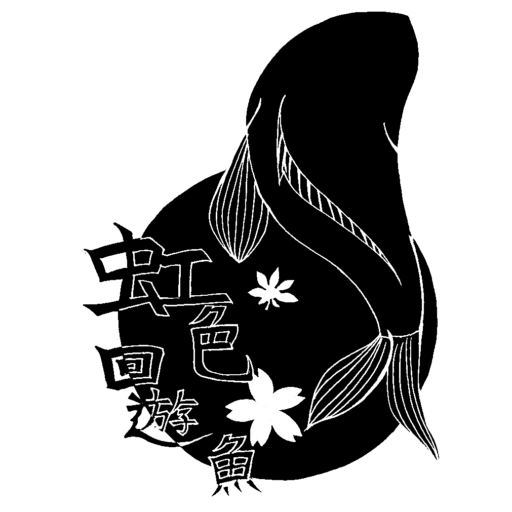戦争にかり出される兵士なんてものは結局使い捨ての駒のようなもので、俺たちの最後の戦いは、白軍の参謀であった色織彩音と、俺の大切な人である黒羽零が相打ちとなるような形で幕を閉じる。当時の俺はそれを遠くで見ることしかできず、彩音が腕を切り落とされたところも、零が彩音に思い切り頭を蹴られて倒れた事も見ることしかできなかった。偶然、本当に偶然で奇跡だと思えるのが、俺の近くにも、彩音の近くにも、旧知の敵軍の人間がいたことだ。お互い息を合わせたように自軍の兵を回収。そして、救護班の元へと走って行った。
頭を蹴られたなら。引き取られた家での教育の中から無意識に思い起こす。確か、頭をぶつけたりした場合は、頭をなるべく動かさないように、意識がたとえあったとしても動かさせないようにするんだっけ。右腕で頭を支えられるように、左腕で彼女の膝の裏に腕を回す。小さい頃に頼まれたお姫様抱っこも確かこんな姿勢だっただなんて思い、そこで走馬灯という言葉が浮かんで頭を振った。違う、これは、違う。零は絶対にこんなところで死ぬような人間じゃ無い。俺が見ていなかったところで「教育」を受けていた彼女。結果として自身を壊して両親だって殺した彼女。彼女は生きるためならば何でもしてきた。こちらに殺意を向けてきたことだってある。今回だってそうじゃないか。
零の部隊長を思い出す。彼女の大切な人は、零が腕を切り落とした彩音だったはずだ。俺だって、軍から離れるまでは彼に世話になっていたし、プライベートで三人で会っていたことだってあった。だから、彼を殺そうとはしないだろう。そう思ってしまったのだった。
零は絶対に生き残る。そう思い直して、意識の無い彼女を運び、応急処置を受けさせ、病院まで付いていき、そして……。
軍の除名通知を運んできたのは誰だったのかを覚えてはいない。優秀だった彼女は身体を動かすことを一切出来なくなっていた。一人で食事を取ることも、歩くことも、排泄行為をすることもままならない。そんな彼女を軍は残しておくことが出来なくなったのだろう。
除名通知を持って現れた女は、俺に「あなたも軍を抜けるの?」と聞いてきた。ずいぶんと見慣れた服装だった気がするが、その言葉にはとげがあった。
当時の俺は、今の俺が言うのもなんだが、クソ野郎だったと思っている。人生を楽しく生きることは罪では無いけれど、自分が快を得るため、幸せになるためだけに生きてきた覚えがあった。それでいて、普通にも憧れていた。だから、彩音のいた白軍から離反して零のいた黒軍に来た俺は、自由を謳歌し、年頃の子供らしく彼女を作ってみたり、バカ騒ぎをして青春を消費していたのだった。
自分の大切なものに目を向けられていなかった。それに気がついたのは「あなたも軍を抜けるの?」という零の部隊長の声だった。その言葉はきっと俺を責めてはいない。けれど、軍を抜けるといったらきっと俺を軽蔑ぐらいはするんじゃ無いかなと思った。
彼女に関して、俺は零の部隊長である、ということぐらいしか知らない。人となりは零と彩音から聞いたことはあるが、お堅い人だなと思って、近づこうとは思っていなかった。でも、彼女は零のことを少なくても思ってくれる優しい人なんだとも思った。
使えない駒になった元軍人が行くところ、それも身体に障害を抱えたものが行くところなんて、理解できない方がまれである。もし、この世界に基本的人権が正しく適応されていて、それでいて誰に対しても優しい世界であるならば。きっと零はこの先でも幸せに生きることが出来るだろう。ただ、そんな現実はない。零は元白軍の人間であるし、それに今は自身の力で抵抗すら出来ない危険な状態にある。そんな上体の彼女を守れる人間がどこにいるだろうか。
「ああ……今の俺に出来る事なんて、これぐらいだからな」
強がって笑顔を向けた。白軍も黒軍も関係ないところに。そのために彼女の病室に車椅子を走らせた。
それからはあっという間に時間が過ぎた。知り合いが誰一人としていないところ。それでいて、零を安心させてやれるところ。白も黒も赤も何も無いところ。飛行機に乗って日本から離れた。世界を廻って、廻って……。結局は戻ってきたけれど、戻った場所は戦争なんて関係の無い離島だった。
軍を離れてからもリハビリを続けたけれど、そもそも首の骨を折って生きている方が奇跡だった。身体は相変わらず動かず、当時より痩せ細ってしまった。それでも、生きている。彼女は戦争から生き残った。二人で逃げていた頃。もう死なせて欲しいと何度か言われたことがあった。それでも彼女を死なせてやれなかった。生きていて欲しかったから。そこには情欲など一切絡まない、ただ、彼女と一緒に生きていたい。そんな想いがあった。軍を離れてから彼女だけが大切だった。
ちょうどお腹が鳴り始めるだろうお昼時。最近は温かくて過ごしやすい季候になった事もあり、なんとなしにベッドの横の窓を開けていた。そこから吹く風にレースが揺らされている。ああ、今日も平和だ。
勝ち取った平和をもしかしたら乱すかもしれないそれをポケットに忍ばせ、零に近づく。最初は義理の兄妹。次は好敵手。同じ軍での仲間。そして、これからは?
こちらを見つめる瞳は優しく、いつものように俺に声をかけてくる。それを遮り、ポケットから小さく四角い箱を取り出す。慌てる瞳は小さい頃に見たままで、思わず笑みを浮かべてしまう。
「なあ、零。こんな俺だけど、俺と……結婚してくれないか?」
彼女の除名の通知を目にしたときに決めたこと。彼女を絶対に不幸にさせない。泣かせない。そんなちっぽけなことすら守れないのかよ。そう思いつつ、目の前で涙を浮かべながらぎこちなく首を縦に振る彼女に、愛おしさを覚えた。