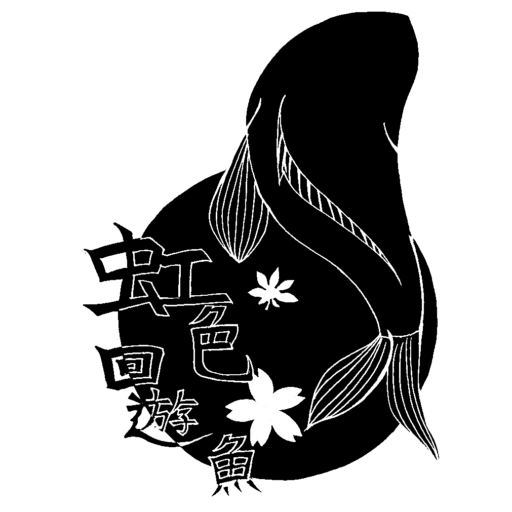深く、深く……。ただ意識だけの存在になって歩き出す。ああ、ここは夢なのだと、そう理解しながらも、夢からどう抜け出せば良いのか分からずにただ歩む。歩くたびに足下が黄金に輝き、私自身の過去を映し出す。
バーで働き始めたこと。直哉に怒られたこと。人を殺しながら笑っていたこと。初めて人を殺したこと。食べ物が無くて人から盗んでいたこと。両親に捨てられたこと。歩めば歩むほどに過去の光景が浮かび上がる。まるで私自身の過去の罪を、無知であったが故の愚かさを思い出させるように。私は一息つきながら目を閉じ、そして思い出すのだった。
物心ついた頃には、毎日生きるので精一杯だった。父のことも母のこともうっすらとしか覚えていない。ただ、毎日殴られて、時には殺されかけて、ご飯なんて用意されていない状態で、放置されるのが常であったことを覚えている。そんな私の状況が変わったのが国内で戦争が起き始めた辺りだった。
黒、白、赤。三つに国内が分かれ、そして毎日どこで戦が起こっているかなどの情報が私の小さな世界を支配する。私の両親はそれぞれの親戚が黒と白の思想が強かったようで、毎日の喧嘩の勢いが増していた。私はただ、自分が殴られるのがイヤで、両親の視界に入らないように縮こまっていた。
ある日、母と父が久しぶりに穏やかに話していた。嬉しかった。だから、森にピクニックに行こうと言われたことになんの疑問も持たずに、両親の手を握ったのだった。それからのことはあまり覚えていない。気がついたら森に一人きり。泣いたって、地団駄を踏んだって両親は戻ってこない。流石に両親にも罪悪感があったのかもしれないけれど、少し歩いたところに廃屋と真新しい食料が詰められたクーラーボックスがあったので、一週間は命を持たせることが出来た。ただ、それからが地獄だった。
食糧も尽き、森から抜け出した私は赤軍に捕まった。そこで何も分からないまま働かされることとなった。毎日金属の筒に黒い粉を詰める作業。火を使うことや金属同士を擦り合わせる事は禁止だ。今では銃弾をその場所で製造していたことは分かるけれど、当時はそんな知識は無い。私と同じような子供達と数年そこで作業をしていたが、ある大人がそこでタバコを吸った事で爆発。ほとんどの人間が亡くなって、私はそこから逃げ出した。
それからは食べ物や金品を人から盗む生活をしていた。時々見つかって怒鳴られることはあったけれど、生きるためには仕方が無い。むしろ生きる邪魔をするなと相手に噛みついたことだってあった。そんな時であった。いつものように盗みを働き、捕まって、相手に殴りかかって。そんなとき、私を捕まえた男の一人が私の首を絞め、同時に舐め回すように視線を投げた。
「なあ。こいつはじゃじゃ馬だけどよ、身体は結構良い感じじゃねえか?」
「ん……?まあ……そうだな」
「それだったらよ、盗んだ分は身体で返してもらうっていうのはどうだ?」
「それは名案じゃないか」
ナイフをギラつかせた男が近づく。殺されるんじゃないかと思うような経験は何度もしてきた。それでもこれからされることに想像が付いて怖かった。きっと犯されるのだろう。時々無理矢理に身体を暴かれて身ぐるみを剥がされたボロボロの何かを横目で見ていたから簡単に分かったのだった。
目をぎゅっと瞑るけれど、手は苦しさから逃げるように、死にかけの虫のようにあちこちにばたつく。そうして、冷たく細長いそれに手が触れた。それからは、記憶がない。
気がついたら辺りは血まみれ。服だってベタベタに濡れて鉄臭い。手に乗っている冷たいそれは、握って少し動かすのがやっとの重さの鎌だった。生ぬるくてひりつくような気持ち悪さ。だけれど、なぜか辺りに散らばるガラスに映っていた自分の口は弧を描いていた。
人を殺した。沢山、たくさん殺した。楽しかった。人の命なんて簡単に消すことの出来るものであった。鎌を振るって、振るって……。そうするだけでお金を手に入れることができ、翌日を生きることが出来た。そんな生活を続けて何年経ったのだろうか。あるときいつも通りに殺しの依頼を受け、命乞いをする老人の首に鎌をかけていたところに彼が現れたのだ。
「この辺りで人を殺しているのはお前だな?」
どこかの人に貢がせるような店からやってきたのかという、目立つ赤と黒。顔だって整っていたけれど、どこかで見た顔のように感じて首を傾ける。そうして二、三秒。ああ、思い出した。目の前で命乞いをしている男と同じように依頼されていた人間だ。大体がとんでもない悪人が多かったけれど、私に対して暗に人殺しをやめるように言ってくるような偽善者だったなんて。
「うん、そうだよ? だったら何かな? もしかして、依頼を諦めて欲しいって話?」
「あー、まあ、そうなるな」
「なに、その歯切れの悪さ」
「お前、人を沢山殺してきたろ。でもな、そんなことをするよりもっと儲かる方法があるって言ったらやめるか?」
「それって……」
きっと娼婦のことだ。
ずっと人を殺め続け、その中で学んだ。私の身体はどうにも使えるらしい。殺される寸前まで私のことを気持ちの悪い目で見つめてくる奴らもいたほどには、使えるのだろう。殺しなんかやめてその道に来ないかと誘われたこともある。勿論そんなことを言ったやつの首は次の瞬間には繋がっていなかったけれど。
目の前の男を殺す算段を立てる。心臓を一突きすれば良いかな。どうにも油断をして売るようだったので、こっちから動き、そうして鎌が弾き飛ばされた。
「もう降参か?」
「っ……!」
鎌を蹴り飛ばされたあと、そのまま腕を取られて引っ張られる。そこに落とされた足に気絶をしないようにと歯を噛みしめつつ、背中に再度落とされた足から逃げようと藻掻いた。
「話は最後まで聞け。俺は赤軍の部隊長。兼、近くの寂れたバーのマスターをしている直哉だ。良かったら、うちのバーで働かないか?」
なんだったらバーの上の部屋に空きがあるから住んでも良いぞ? そんな甘い言葉を囁いてくる男。いつの間にか殺害対象だった男は逃げ出してしまった。交渉という名の強制にため息をつきたくなる。証拠に、背骨を綺麗に踏みしめている足は、もう少し力を入れたら簡単に私の腰の骨を折ることが出来るだろう。もう降参だと両手を伸びをした亀のように広げて首を縦に振ったのだ。
でもまさか、この後直哉がどんどんと人を保護して、最終的に十人近くで住むことになるとはこの頃の私は思っていなかったのだった。