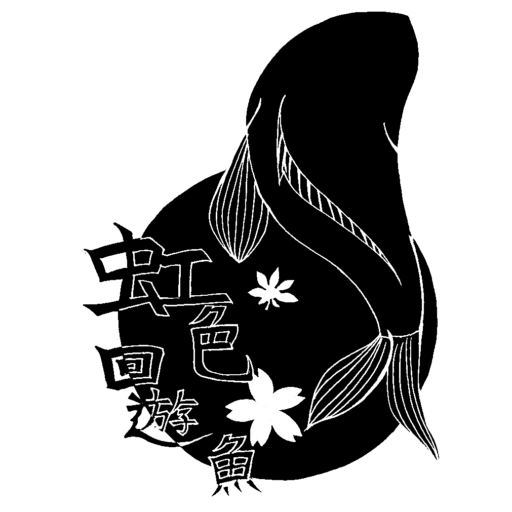『おいで、おいで』
そう声が聞こえて、いつもの夢だと理解する。霧雨が降る、須賀くんと森の中で起こした奇跡の季節。
目の前にはお母さんを探す少年が、森の中へと歩いていた。お母さん、と進む彼の姿は次第に変化していき、あの日の私のもとへとつく。そして、逃亡の果てに私を閉じ込めて一人で―――。
夢だとわかっていながら、飛び起きるように体にかけていたものを弾き飛ばす。隣で眠っていた彼はこの時期になると私がその夢を見るとわかっているのか、慌てたようすで起き出して、キッチンへ向かう。きっと数分後にはおろおろとしながらもあたたかい牛乳を持ってきてくれるんだろうと思いつつ、ぎゅっと体を抱き締めた。
『もし、あのときに解決できなかったら、須賀くんはどうしていたの?』
そう彼に聞いたことはなかったけれど、思い出した今ならわかっている。彼は夢の中と同じようにしていただろう。それか、私の記憶をもう一度奪って、最後まで自分一人で抱え続けることになるだろうことも簡単に予測できた。
本当につらいことは自分一人で抱えこんで逃げ出さない、自分が傷つくだけならば耐えてしまう優しい人。私には見つけられない綺麗なものをたくさん知っている人。…それでいて、残酷な人。付き合い始めて数年たっても昔から変わらない、須賀君はそんな人だ。
「しぃちゃん……その、えっと」
「…なぁに、須賀くん?」
夢を思い出して震える体を彼から隠すように布体に布団をかけ直す。果たして彼は、想像している通りの姿で湯気のたつカップを片手に目線を合わせてくる。その姿に小さい頃の姿が重なって、笑みがこぼれると、何を勘違いしたのか、それとも私の想像したことを理解したのか、目の前の彼は耳まで赤くさせながら眉を潜める。
残酷で、それでいて昔から守りたくなるようなかわいい人。それから。
「しぃちゃん……。悲しいって気持ちから、目を背けないで。僕は、しぃちゃんに笑っていてほしいけど、無理してほしいわけじゃ……ない、から」
誰よりも人のことを見ていて、誰よりも優しい人。
まるで自分のことのように悲しそうな、辛そうな目でこちらを見ていて、それに気遣うような温かさも込められた瞳。須賀君の代わりに虚勢を張って、男の子たちと喧嘩した後に、彼が見せた瞳と同じ色。本当に昔から変わっていないんだ、と改めて思いながらも目に浮かんできたあたたかいそれを拭う。
「うん、…ありがとう、須賀くん」
「ううん、それは…きっと僕が…僕が選んだもう一つの選択だから、お礼を言われることじゃなくて、……その、あの時に考えていた選択肢は変えられないから、ごめん。でも、僕は、……今の僕はしぃちゃんも守るし、しぃちゃんの幸せも守りたいと思っているから」
カップをサイドテーブルに置いた須賀くんに、そのまま拭いきれなかったそれを拭われて、抱きしめられる。
「しぃちゃんのことも守る。でも、しぃちゃんが思ってくれているぼくのことも、大切に、する」
すぐ横に見える彼の耳は真っ赤になっていて、つられて赤くなりつつも「うん」と小さくつぶやいた。